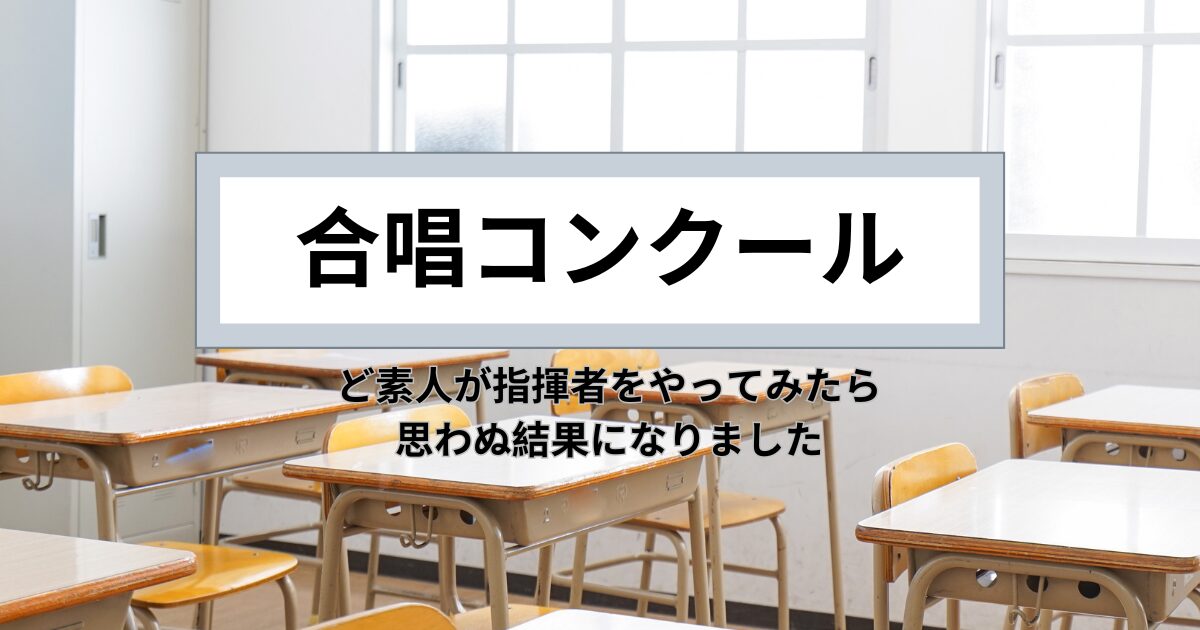目次
指揮者に求められる6つの資質…うちの子には全部なかった?
我が家の子ども達は、娘も息子も中学時代の合唱コンクールで指揮者になりました。指揮者=リーダー・気が強い・度胸があるなどのイメージだったのですが、二人とも真逆な生徒。
両親も「ザ・体育会系」でしたので、音楽経験はなし!何をどうアドバイスしてあげるべきか、全くわかりませんでした。
そもそも、指揮者に必要と言われているのは、こんな資質だそうです:
- リーダーシップ
- コミュニケーション能力
- 音楽への理解
- 表現力
- 責任感
- 協調性
- ポジティブ思考
娘も息子も、どれにもバッチリ当てはまらないんですよね(笑)何故そんなことになったのか、今でも不思議です。
それでも「やってみたい」と言った理由
そんな子が、ある日ふと「指揮者やってみたい」と言い出しました。
正直、びっくりしました。
「本当に大丈夫?」「練習大変だよ?」「人前だよ?」と何度も聞きました。まずは、「立候補できるの?」そこからでした。
でも、娘は「やってみたい」とだけ。
理由は、「指揮者の先輩がかっこよかったから」だそうで。
なんだか、それだけでもう十分。理由なんて、動機なんて、なんだっていいんですよね。
「やってみたい」と思った時点で、もうそのチャレンジは意味がある。
そして6年後、息子の指揮者になりたい理由は、「姉ちゃんがかっこよかったから。俺にもできるかな、、、。」と、性格的におとなしく、前に出たがらない息子が言った時には、青天の霹靂でした(大げさですが)
親もど素人だけど、一緒に学んでサポートした
とはいえ、やるからにはちゃんとやってほしいのが親心。
「4拍子って?」「楽譜がわかんない」「手の振り方ってどうするの」――
そんな子どもの声に、音楽ど素人の私も、人生初の『指揮法』について検索しまくる日々。
- YouTubeで中学生の指揮動画を一緒に見る
- テンポを口で言いながら一緒に練習
- 楽譜を印刷して、一緒にページをにらむ
- 一音一音の雰囲気や歌詞の意味も一緒に読み込む
- 毎晩、自宅で練習の日々
- クラスメートとの相談を受ける ・・・etc
音楽の専門知識は全然ないけれど、応援する気持ちだけは100点満点だったと思っています。
緊張で手が震えながらも、しっかりやり切った当日
当日、体育館の舞台に立った我が子は、やっぱり緊張でガチガチ。
遠くからでも、指先が小さく震えているのが分かりました。
以外なのですが、どちらかというと明るいタイプの娘は、真顔で必死、「顔、こわっ!」でした。おとなしくて、人前で話すのが苦手な息子は、合唱前にステージのクラスメートに向け「変顔」をして和ませる余裕がありました。人とは分からないものだなと感じました。
でも、最初の一音が始まると、真剣な顔つきに。
拍に合わせて、一生懸命腕を振り続ける姿に、そしてクラスメートのみんなと一つになっている姿を見ながら、思わずジーンときました。
終わった瞬間、全体を包むような拍手。
先生からの講評では、「一生懸命に皆を導いていた姿が印象的だった」と言葉をいただき、二人とも「指揮者賞」まで受賞することができました。
何より、我が子のクラスが、目標を達成してみんなで喜んでいる姿にとても感動しました。音楽的な評価はよくわからないけど、一つの目標に向かって、クラスみんなで努力する姿に胸が熱くなりました。
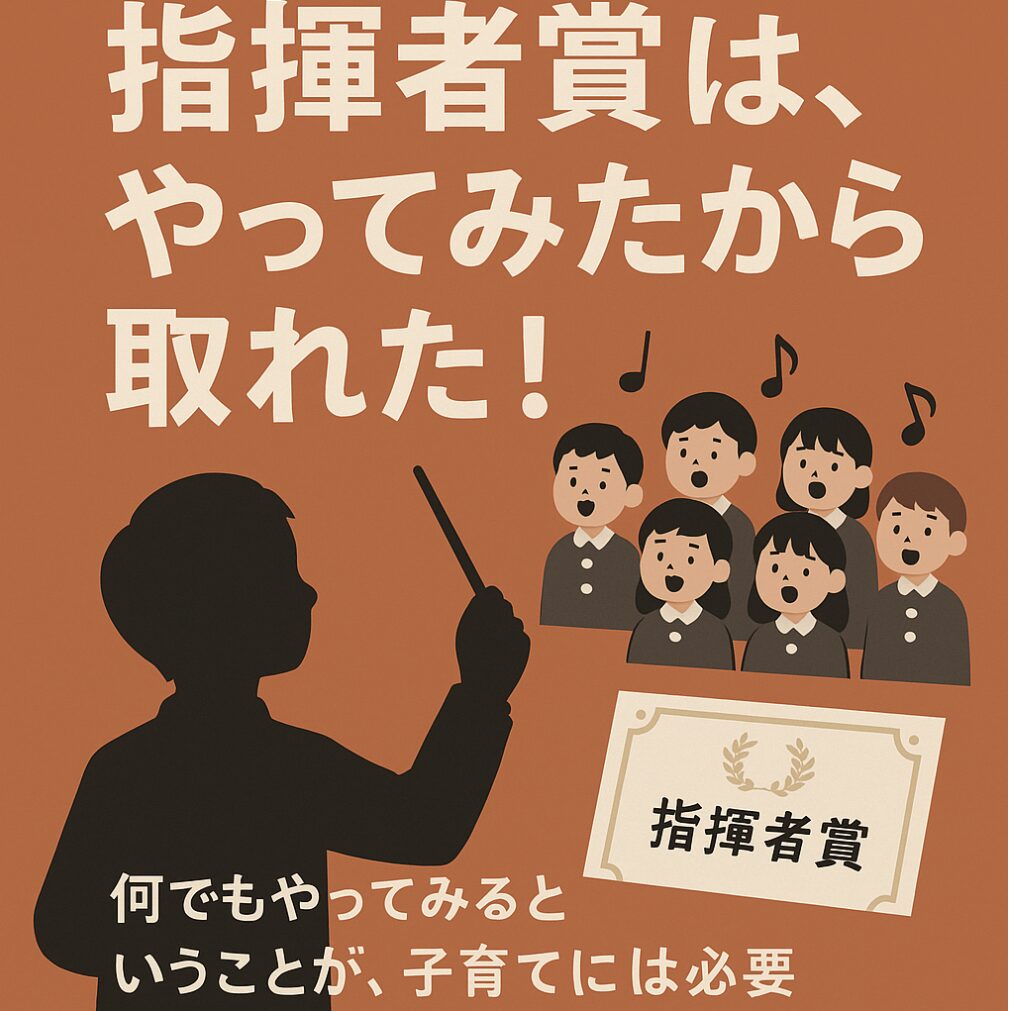
チャレンジの結果、自信と積極性が育った
終わったあと、本人が一番驚いていました。
「緊張して、ちゃんと振れてなかったかも…」と心配していたくらいだったのに。
でも、表情は達成感でいっぱい。
この経験をきっかけに、普段の学校生活でも前向きな姿勢が増えたように思います。
- クラスの係に自ら立候補
- 苦手だった発表も、少しずつ堂々と
- 「チャレンジするの、けっこう楽しいかも」とポツリ
子どもの中で、何かが確実に変わった瞬間でした。
合唱コンクールにチャレンジした子ども達の変化は、こんな感じでした。
| 指揮者に必要な資質 | わが子の実際の様子 | 成長したポイント |
|---|---|---|
| リーダーシップ | 人前で仕切るのが苦手。前に出るのは避けがち。 | 皆の前で手を挙げて意見を言えるように。 |
| コミュニケーション能力 | 伝えるのが苦手。言葉で指示するのは不安だった。 | 合唱メンバーと話し合って練習時間を調整できた。 |
| 音楽への理解 | 楽譜が読めなかった。リズムも曖昧。 | 自分で拍を数えながら練習し、曲の流れを覚えた。 |
| 表現力 | 最初は棒立ち。恥ずかしさが先に立っていた。 | 動きに抑揚が出て、表情も豊かに。 |
| 責任感 | 途中で「やっぱり無理かも」と言っていた。 | 本番までやりきり、自信につながった。 |
| 協調性 | 合唱メンバーとの温度差に悩んでいた。 | 相手の意見を聞きながら、雰囲気を整えるよう努力。 |
| ポジティブ思考 | 「失敗したらどうしよう」と不安が大きかった。 | 「次はもっと上手くやれそう」と前向きに。 |
「向いてない」なんて決めつけないで。親も一緒に挑戦すればいい
この経験から、私が強く感じたこと。
「向いてるかどうか」なんて、やってみなきゃわからない。
たとえ向いてなかったとしても、やってみたことがすでに尊いし、意味がある。
子どもが挑戦したいと思ったとき、親ができるのは“可能な限り応援すること”。
専門家じゃなくたって、知識がなくたって、そばで支えることはできる。
そして、たとえ小さなきっかけでも、子どもの中にある「やってみたい」気持ちを信じてあげることで、
その先に自信や積極性が芽生えることだってあるんです。
おわりに|「何でもやってみる」が、子どもを強くする
子育てって、つい「失敗しないように」とか「無理のない道を」と考えてしまいがちだけど、
遠回りでも、泥くさくても、ちょっと背伸びでも、「やってみる」ことにこそ意味があるんじゃないかなと実感しました。
親が先回りして判断せず、まずはやらせてみる。
そして全力で応援する。
それが、子どもにとって最高の成長チャンスになるかもしれません。