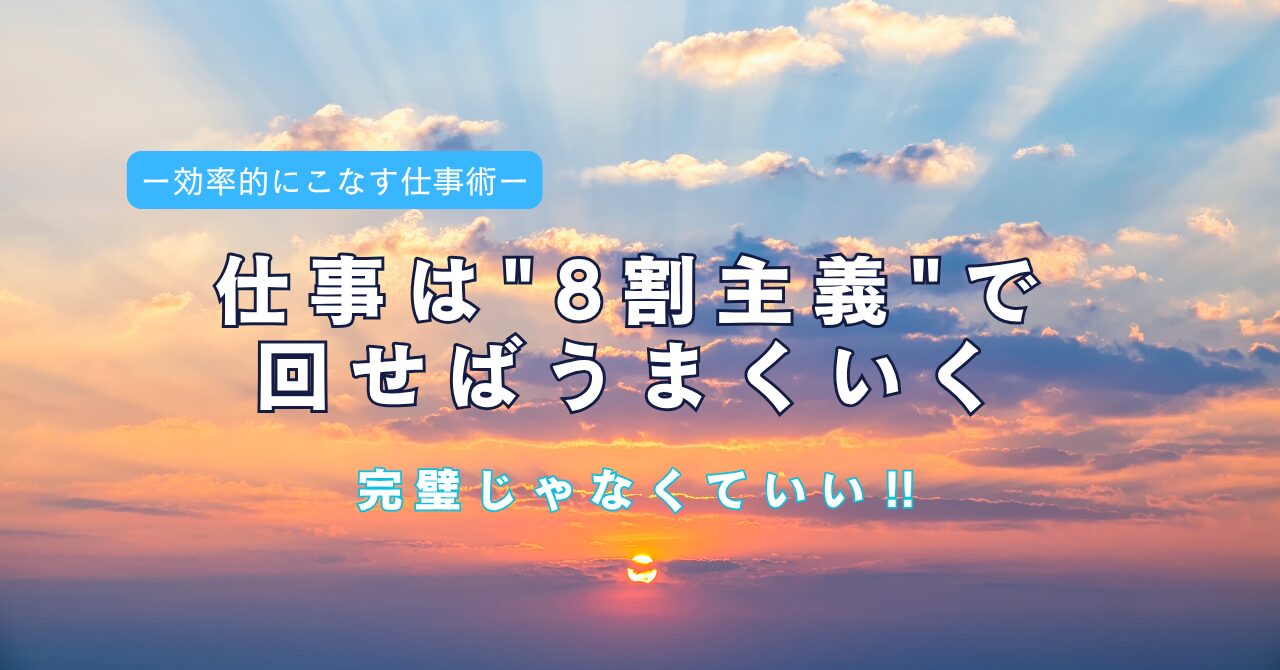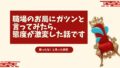目次
はじめに:「完璧じゃないとダメ」と思い込んでいませんか?
「これで本当に大丈夫かな…」
「もっと丁寧にやらないと」
「完璧に仕上げないと評価が下がるかも」
そんな風に、自分にプレッシャーをかけながら仕事をしていませんか?
でも、実は仕事の成果って、10割で仕上げても8割で仕上げても、周囲の評価はそれほど変わらないことも多いんです。
むしろ、常に完璧を目指して時間をかけすぎることが、逆に評価を下げてしまうケースもあります。
今回は、「8割で仕上げる」ことのメリットと、複数のタスクを効率的に回すための考え方についてお伝えします。
なぜ“8割仕上げ”でも大丈夫なのか?
①受け手はそこまで見ていない
資料を提出する時、「文字揃えは整っているか」「表現にムラがないか」など、細部にまでこだわる人は多いです。
でも、その資料を読む上司やクライアントは、全体の構成や要点が伝わっているかどうかを重視しています。
たとえば会議資料や報告書であれば、「結論が明確か」「次に何をすればいいかわかるか」が重要で、
フォントサイズや細かな表現の言い回しまで見ていないことがほとんどです。
つまり、自己満足的な完璧さは、相手にとってはオーバースペックであることも。
②完璧を求めるとスピードが落ちる
「完璧主義」は、仕事の質を高める反面、スピードを犠牲にしがちです。
資料の推敲を何度も繰り返したり、細かな修正に時間をかけたりしていると、他のタスクが後回しになります。
現代の仕事はスピード重視。
60点で即出す人のほうが、100点で3日後に出す人より評価されることもあります。

8割で進める仕事術とは?
①最初にゴールと合格ラインを決める
仕事を受けたらまず、「どこまでやれば合格なのか」を確認しましょう。
たとえば、「この資料は社内確認用だから、簡潔でいい」とか、
「これはお客様に渡す最終資料だから、丁寧に整えるべき」など。
タスクの重要度に応じて“8割でよし”とする基準を明確にすることで、無駄に手をかけすぎることを防げます。
②まずは“ラフでもいいから出す”
報告書や提案書など、完成形にこだわるより、まずドラフト版を出して反応を見ることも大切です。
特に、何度も修正が入るような仕事は、
最初から完璧に作っても結局作り直しになることが多いです。
「仮で作ってみました」と言って見せると、フィードバックがもらいやすくなり、効率よく完成に近づけます。
③「完了優先」でToDoリストを回す
仕事が多すぎて手が回らないときは、ひとつずつ完璧に仕上げようとするより、“完了”を優先するのがポイントです。
特に、日常業務やルーティン作業などは、精度よりもスピードと回転率。
「80点でも今日は終わらせよう」と意識するだけで、精神的な負担も軽くなります。
完璧を求めがちなタスク一覧と“8割対応”の例
以下の表は、仕事の現場で「完璧を求めがち」なタスクと、それに対する「8割でOK」な対応例です。
| タスク内容 | ありがちな完璧主義 | 8割仕上げのコツ |
|---|---|---|
| 会議資料の作成 | 図表の装飾、色使い、文字揃えを徹底 | 構成と要点が伝わることを重視。デザインは最低限 |
| 社内メール | 表現や言葉遣いを何度も見直す | 結論→理由→依頼の3構成で簡潔に送信 |
| 報告書 | 推敲に推敲を重ねる | 事実と要点を先にまとめて早めに提出 |
| チェック業務 | 一文字ずつチェックして時間をかける | 重要箇所に優先的に集中し、あとはスキャン的に確認 |
| 部下や後輩へのフィードバック | 全てを丁寧に書き込む | ポイントを一つか二つに絞って、後は対話で補足 |
「丁寧すぎる=良い仕事」とは限りません。
“適切な粗さ”が、効率と成果を両立させます。
それでも「8割でいい」が不安な人へ
「8割で出して怒られたらどうしよう」
「手抜きと思われない?」
そんな不安がある人は、先に上司やチームと期待値をすり合わせておくと安心です。
「急ぎなのでラフですが、方向性だけご確認ください」
「この件、まずざっくりで良いですか?」
そんなひとことがあるだけで、受け手の印象は全く変わります。
おわりに:「完璧じゃなくていい」を許そう
完璧を目指すことが悪いわけではありません。
でも、それによって疲れきってしまったり、他の仕事に支障が出てしまっては本末転倒です。
8割でもちゃんと伝わる、評価される、間に合う。
そんな経験を少しずつ積み重ねていけば、「8割でOK」という感覚が身についていきます。
肩の力を抜いて、“うまくやる”より“うまく回す”仕事術を。
あなたの働き方が、もっと軽やかで、もっと成果の出るものになりますように。