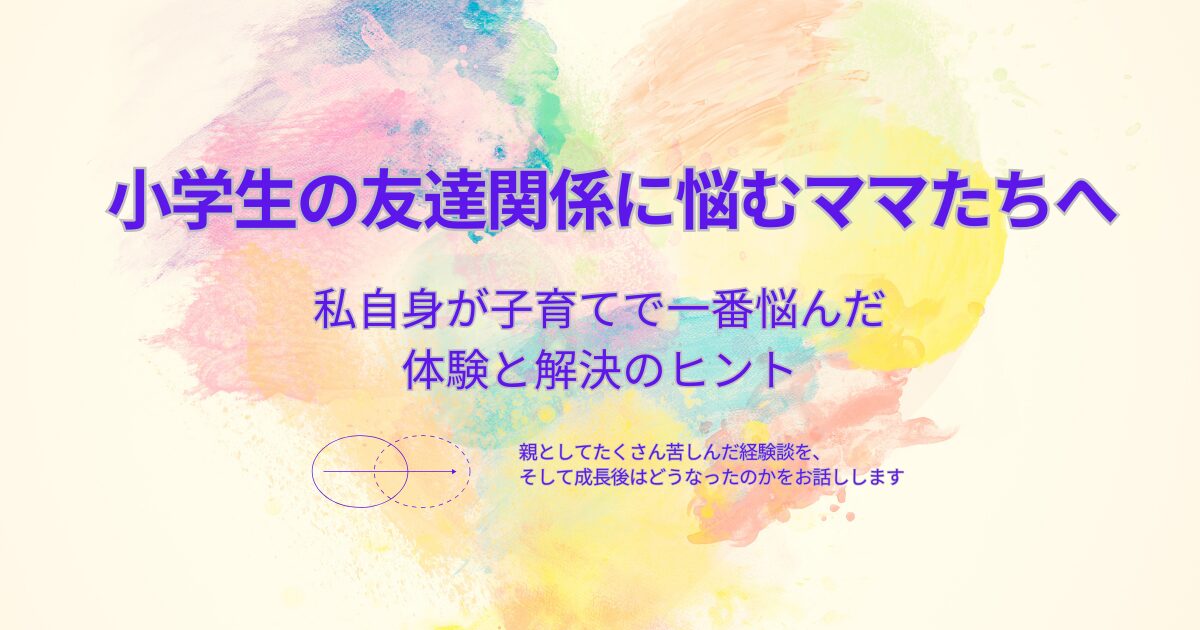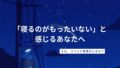目次
小学生の友達関係は、私自身、子育てで一番悩んだテーマです。誘われない・からかわれる子どもへの安心できる接し方と、親のサポート法を体験談から紹介します。
友達の定義とは⁉
「子どもが友達に誘われなくなった」
「大勢の輪に入れない」
「いじめではないけれど、からかわれることが多い」
小学生の友達関係は、親にとって一番気になるテーマのひとつです。特に低学年から高学年にかけては人間関係がめまぐるしく変化するため、「わが子は大丈夫だろうか」と心配になってしまいますよね。
私自身も、娘と息子の友達関係にはずっと悩みを抱えていました。二人とも比較的おとなしい性格で、積極的に大勢の輪に入るタイプではなく、友達は多いほうではありませんでした。
仲良くなったお友達がいても、別の積極的な子が連れて行ってしまい、我が子は仲間はずれ。
お家遊びの約束をして待っていると、「別の子と遊ぶ」と言われドタキャンになったり。
低学年の頃は「遊びに誘われなかった」と涙ぐむ日もあり、親として心が痛みました。子育ての中で、体調面以外で一番悩み苦しんだことだと思います。高学年になり、中学生になっても、友達関係のことでは、思い悩んでいたことを忘れることができません。
しかし成長するにつれて、友達は「数ではなく質」であること、そして「一人でも自分の意志で進める強さ」を持つことが大切だと気づかされました。
今回は、そんな経験を踏まえながら 「小学生の友達関係の悩みと親の向き合い方」 を整理してお伝えします。
小学生の友達関係、親が抱える代表的な悩み
小学生の友達関係は「仲良しグループに入れるかどうか」が大きなポイントになります。親がよく直面する悩みを整理すると、次のようになります。
| 親の悩みのパターン | 具体的なシーン | 親の気持ち | 子どもへの影響 |
|---|---|---|---|
| 仲良しの子に誘ってもらえない | 放課後の遊びや誕生日会に呼ばれない | 「嫌われているのでは?」と不安 | 孤独感を抱くこともある |
| 大勢の輪に入れない | クラスや公園で大人数で遊んでいるのに端にいる | 「社交性が足りないのかな」と心配 | 少人数や一人で遊ぶことで満足するケースも |
| からかわれる対象になる | 行動をばかにされる・体型や服装をいじられる | 「いじめに発展しないか」と不安 | 自尊心が傷つくこともある |
| 友達が少ない | いつも同じ子とだけ過ごす | 「もっと交友関係を広げてほしい」 | 安心できる関係を大切にする力が育つ |
こうして見てみると、悩みの根本には「親自身の不安」があることが分かります。
親としては「友達が少ないのは良くないこと」「大勢に入れないのは心配」と感じてしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。
私も「なぜ自分から積極的に行けないのか」などと、我が子に問い詰めたことがありました。まさに、自分の不安やイライラをぶつけていた弱い親だったと反省しています。
わが家の体験談|友達が少ないことは本当に悪いこと?
娘も息子も幼い頃から控えめな性格で、休み時間も決まった友達と静かに過ごすことが多い子どもでした。
低学年の頃は「遊びに誘われなかった」としょんぼり帰宅したこともあり、私も胸が痛くて「どうにかしなきゃ」と思い詰めたこともあります。
けれど振り返ると、我が子は「少ないながらも安心できる友達」を大切にし、その関係の中で自分らしく過ごしていました。高学年になると、少しずつ自分の意志で行動できるようになり、「無理に輪に入らなくてもいい」という気持ちが自然と育っていたのです。
友達の「数」にこだわらなくてもいい。むしろ少ないからこそ「信頼できる友達を見極める力」や、「一人で過ごす強さ」を育てることができたのだと思います。

小学生の友達関係に悩む親ができるサポート
では、子どもが友達関係で悩んでいるとき、親はどうサポートすればよいのでしょうか?
いくつかのポイントを整理しました。
まずは話を聞いてあげる
「そうなんだね」「それは嫌だったね」と、子どもの気持ちに共感することが一番大切です。アドバイスよりも「聞いてくれる」存在が子どもに安心を与えます。
自宅が安心できる場であることは、子どもにとって気持ちを落ち着かせることができる大切な事です。
「友達は多ければいい」という価値観を手放す
「友達が少ないのは悪いことではないよ」「無理に合わせなくてもいいんだよ」と伝えてあげることが、子どもの自信につながります。
得意なことを見つけて伸ばす
習い事や趣味を通じて自分の強みを発揮できれば、友達関係にも良い影響を与えます。子ども同士の共通の話題が生まれることも多いです。
自分に得意なものがあると、自然と自信につながって、少しずつですが積極性も育っていきます。
深刻な場合は学校へ相談する
からかいが強くなったり、子どもが苦痛を訴える場合は、担任や学校に早めに相談を。子どもが孤立する前に周囲と連携することも大切です。
***関連記事***

成長とともに友達関係は変化する
小学生の友達関係は、成長とともに必ず変化します。
高学年から中学生、高校生、大学生になると環境が大きく変わり、新しい友達ができるチャンスも増えます。
「小学生の頃、友達が少なかった」
「誘われなくて寂しい思いをした」
そうした経験も、やがて「自分のペースで行動できる強さ」や「信頼できる人を見極める力」につながります。
私の子どもたちも、決して友達が多いタイプではありませんでしたが、大人になった今は「自分の価値観を大事にする」人間関係を築けています。
よくある悩み(Q&A)”私も経験しました”
Q1. 子どもが「遊んでもらえない」と泣いて帰ってきたら?
A. まずはしっかり抱きしめて「そうだったんだね」と受け止めてあげてください。すぐに解決策を与えるよりも、安心感が先です。その上で「一人でも大丈夫だよ」「一緒に楽しいことしよう」と家庭で安心を補ってあげましょう。
Q2. 友達が少ないままでも将来困らない?
A. まったく困りません。むしろ「狭く深い関係を築ける」力が育ちます。大人になってからの友人関係や職場での人付き合いに生かされることも多いです。
Q3. からかわれるのと、いじめの境界は?
A. 子どもが「嫌だ」と感じているのにやめてもらえない場合は、いじめに近い状態です。深刻になる前に先生や学校に相談しましょう。
経験上、男の子はあまり自分から話さない場合もありますので、日々の変化をよく見てあげることが必要です。決して問い詰めるのではなく、自分から話す状況を作ってあげて下さい。
まとめ|友達関係は子どもの成長の一部
小学生の友達関係に悩むのは、どの親も同じです。
「仲間に入れない」「誘われない」と聞くと不安になりますが、友達の数や輪の大きさがすべてではありません。
大切なのは、
- 子どもが安心して過ごせる関係を持てているか
- 自分の意志で行動できるようになるか
- 成長の中で人間関係を変えていける力を育んでいるか
という視点を持つことです。
友達関係の悩みは、子どもの成長に寄り添うチャンスでもあります。親ができるのは、過剰に心配するのではなく「見守りつつ、必要なときは支える」こと。
友達は多ければいいというものではありません。子どもが「自分らしく生きられる」ようにサポートしてあげることこそ、親にできる最も大切な関わり方だと実感しています。
社会人となった我が家の子どもたちを見て、小さい頃、あんなに悩んでいたことが信じられないほど、周囲との関係性を程よい距離感で構築しています。
相変わらず友達は多くないし、一人で行動することもあります。でも、会社の人間関係をうまくやり過ごすスキルや、悩みから逃げずに自分で考える力は、今までの環境で養われた強さだと思っています。