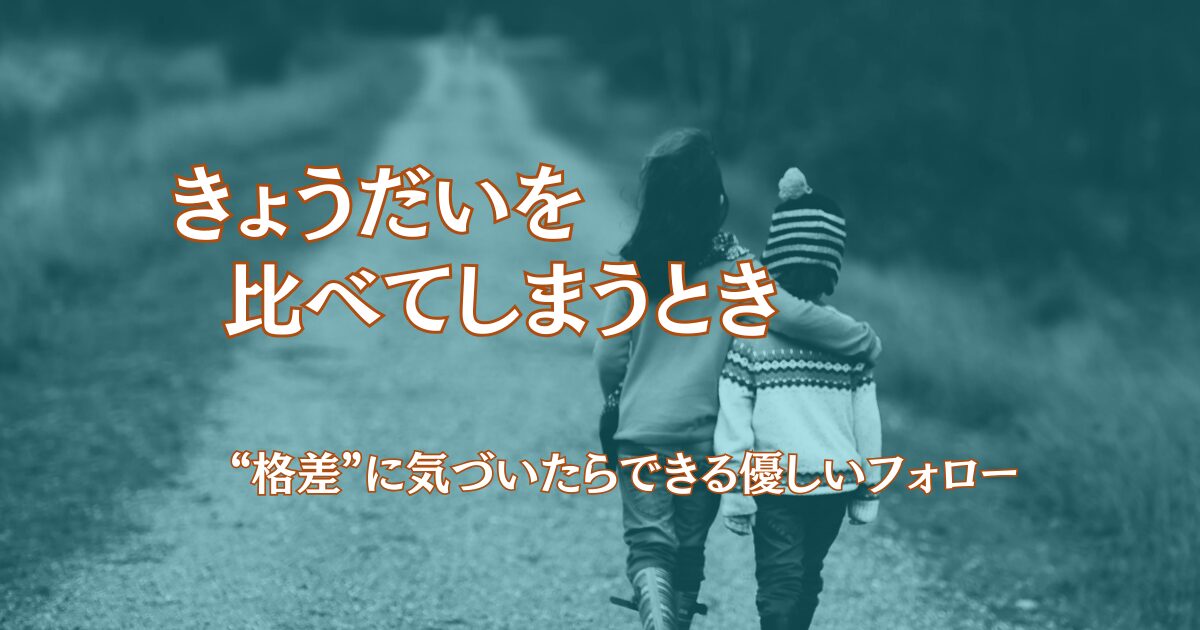目次
はじめに:同じように育てているのに「差」が出てしまう不思議
「上の子には厳しくしてしまう」「下の子には甘くなる」──。そんなことはありませんか。
多くの親が心のどこかで感じている“きょうだい格差”。
「できるだけ平等に育てたい」と思っていても、現実には無意識のうちに扱いが変わってしまうことがあります。たとえば、上の子には「お姉ちゃんなんだから我慢して」と言ってしまう。下の子には「まだ小さいんだから仕方ない」と甘やかしてしまう。
その差は小さなことに見えても、子どもの心には“格差”として積み重なり、自己肯定感やきょうだい関係に影響を与えることがあります。
我が家は、大人になっても「自分は大学を選べなかったけど、弟は自由に選ぶことができてずるい。」など、様々な思いが心の中にあるようでした。
でも、親としてことあるごとに反省し、軌道修正したことで、姉と弟はお互いを認め合い、自分に足りない部分を持つきょうだいを、リスペクトしながら成長することができました。今では、とても仲の良いきょうだいとなりました。
この記事では、きょうだい格差とは何か、その影響、そして親ができるフォロー方法について、体験談を交えながら発信していきます。
きょうだい格差とは?よくあるケース
無意識に生まれる差
きょうだい格差とは、親の態度や期待が子どもによって異なり、その違いが子どもに不公平感を与えてしまうことを指します。
「意図的に差をつけているわけじゃないのに…」という親が大半です。
ですが、子どもはとても敏感で、親の言葉や態度の微妙な違いを感じ取ります。
よくあるきょうだい格差のパターン
- 上の子へのケース
- 「お姉ちゃん(お兄ちゃん)なんだから我慢しなさい」
- 家事の手伝いや面倒を頼まれることが多い
- 成績や行動に対して「できて当たり前」「なぜできないの」と思われやすい
- 下の子へのケース
- 「まだ小さいから」で失敗が許される
- 甘えさせてもらえることが多い
- 上の子と比べられ「お姉ちゃんはできたのに」と言われる
結果として…
- 上の子は「責任感が強くなる一方で我慢が多い」
- 下の子は「甘え上手だが自立が遅れる」
- きょうだい関係にもライバル心や嫉妬が生まれる
***関連記事***
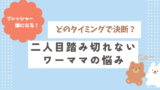
きょうだい格差が子どもに与える影響
上の子への影響
- 我慢が習慣化する
いつも「我慢して」と言われ続けると、自分の気持ちを抑えるクセがつきます。
大人になってからも、自分の意見を言えずにストレスを溜めやすくなることがあります。 - 認められていないと感じやすい
「できて当たり前」という扱いを受け続けると、努力をしても褒めてもらえないと感じやすくなります。
結果として、自己肯定感が下がりやすいのです。 - 責任感が強すぎる
良い面としてはリーダーシップを発揮することも多いですが、「常に期待に応えなければ」というプレッシャーを背負いやすいのも特徴です。
下の子への影響
- 自立が遅れやすい
失敗しても「仕方ない」と見過ごされやすいため、チャレンジ精神や責任感が育ちにくい場合があります。 - 上の子と比較されて劣等感を抱く
「お姉ちゃんは積極的だったのに」と言われると、努力よりも「どうせ自分はできない」という気持ちを持ちやすくなります。 - 甘え上手で人間関係に依存しやすい
小さい頃に甘やかされると、大人になっても人に頼りすぎる傾向が出ることもあります。
きょうだい関係への影響
- 競争心や嫉妬心が強くなる
親の愛情を取り合うような感覚が根づき、仲良くできない場合もあります。 - 距離ができることもある
大人になってからも「不公平だった」という気持ちが残り、関係がぎくしゃくすることも。
親ができるフォローの方法
同じだけ話を聞く
一人ひとりに「自分だけの時間」を持たせてあげることが大切です。
毎日長時間でなくても、1日5分のマンツーマン時間で十分。
「今日はどうだった?」と上の子、下の子それぞれに向き合うだけで安心感につながります。
比較ではなく「その子らしさ」を認める
「お姉ちゃんはできるのに」ではなく、
「あなたはあなたらしくていいね」という言葉を意識しましょう。
違いを受け入れられると、きょうだい同士も自然とお互いを尊重できるようになります。
期待値を調整する
- 上の子には「頼りにしてる」だけでなく「甘えていいんだよ」と伝える。
- 下の子には「できるよね」と信じて任せる機会をつくる。
このバランスが大切です。
褒め方を工夫する
結果だけでなく努力や過程を褒めるようにしましょう。
例)
- 「テストで100点すごいね!」よりも「毎日コツコツ勉強したのが伝わってきたよ」
- 「お片付けできたね」よりも「最後までやり切ったのが偉いね」
努力を見てもらえた子どもは「自分は価値がある」と感じられます。
周囲との比較から親自身が抜ける
つい「上の子はああだったのに」と思ってしまいますが、子どもは一人ひとり違う存在です。
まずは親自身が“きょうだい比較”をしないこと。
完璧にできなくても、「あ、比べちゃったな」と気づいたときに修正すれば十分です。
体験談:上の子への厳しさに気づいたとき
私自身も、年齢が離れていたこともあり、上の子には「お姉ちゃんだから」とつい厳しく接してしまっていました。下の子が泣いていると「我慢してあげてね」と上の子に頼んでしまい、後で「私ばっかり…」と泣かれたことがあります。
そこで意識的に「上の子だけと過ごす時間」を増やしました。
一緒に買い物へ行ったり、寝る前に少しだけ2人だけで話したり。
それだけで、上の子の表情がやわらかくなり、「お母さんは私のこともちゃんと見てくれてる」と思えるようになったのです。
小さなフォローでも、子どもにとっては大きな安心につながります。
まとめ:完璧でなくて大丈夫、気づいたときに修正すればいい
きょうだい格差は、どんな家庭でも起こり得るものです。
大切なのは「差をゼロにすること」ではなく、子どもが“不公平だ”と感じないように意識すること。
- 同じだけ話を聞く
- 比較しないで、その子らしさを認める
- 上の子に甘えるチャンスを、下の子に自立の機会を
親も完璧ではありません。体調や気分でも、左右されることはあります。
「今日は比べすぎたかな」「下の子ばかり甘やかしたかも」と思ったら、明日少しだけ修正すればいいのです。
きょうだい格差は、親のちょっとした意識の積み重ねでやわらげることができます。
そして、それが子どもの自己肯定感と、きょうだいの良い関係を育む大切な土台になります。