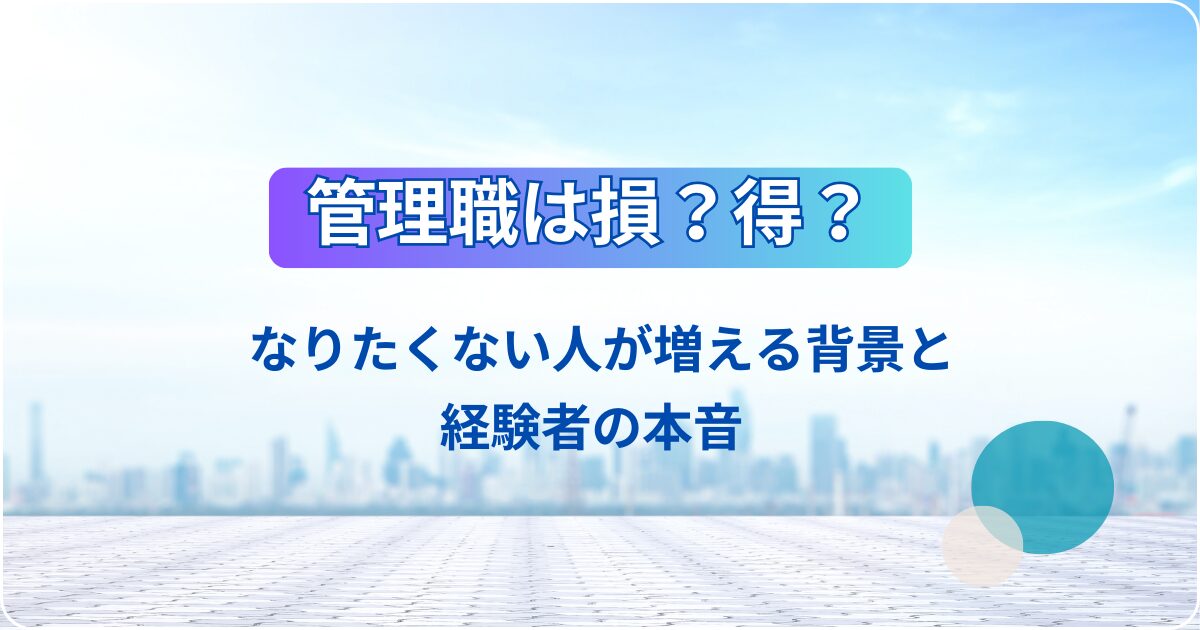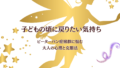目次
管理職と非管理職、組織の一員として、考える場面は必ずあると思います。
最近では、「管理職になりたくない」と考える人が増えているようです。
特に若い世代では「プライベートを大事にしたい」という声が強まっています。ワーママでは、子育てと仕事の両立に悩み、管理職への道をあきらめるパターンもあることでしょう。
役職者への登用減少を防ぐため、部下に、「管理職になりたくないと思わせてはいけない」「愚痴や不満は決して見せてはいけない」などの指導がある会社もあります。
私も「昇進したらやりがいもあるし、給料も上がる、生活が安定するよ」「あなたの働きぶりなら、役職は当然だよ」など、思いもかけず認めてもらえたことが嬉しく、管理職となり現在に至っています。
現在の会社に転職して6年、4年前から管理職を務めていますが、本当によかったのか…。
定年が見えてきた今、自分のキャリアを振り返りながら、管理職を経験して良かったこと・つらかったこと、そして管理職と非管理職のリアルな違いをまとめたいと思います。
管理職になりたくない人が増えている理由5選
まずは、管理職を敬遠する人が増えている背景を整理してみましょう。
責任に比べて報酬が少ない
かつては「課長になれば年収が100万円単位で上がる」といった時代もありました。
しかし最近は昇給幅が縮小し、責任の重さに見合わないと感じるケースが多いのが現実です。
「部下のミスも自分の責任」「成果が出なければ上層部から叱責」――それに対して給与は数万円程度の差。
「だったら現場で専門職として働いていた方がいい」「自己研鑽を積むことが、転職にも有利になるはず」と考えるのも自然です。
ワークライフバランスが崩れる
管理職になると、会議や資料作成、上層部への報告が増えます。
現場仕事だけをしていた頃と違い、「定時で帰る」「休日は完全に休む」が難しくなります。
休日でもスマホやパソコン気にしてしまう、家族との時間に集中できない――。
実際、私自身も旅行先で緊急連絡が入り、半日ホテルで電話対応に追われたことがありました。
上下の板挟み
管理職は「会社の方針を伝える人」であると同時に、「部下の声を吸い上げる人」でもあります。
そのため、上からも下からも不満が集まる立場になりがちです。
部下からは「現場をわかってない」と言われ、上からは「数字を出せ」と言われる。
その間で調整し続けるのは、大きなストレスとなります。
部下育成のプレッシャー
今の管理職に求められるのは「人を動かす力」よりも「人を育てる力」です。
しかし、「自分は教えるのが得意じゃない」「部下との関わりがストレス」という人にとっては荷が重く、昇進をためらう理由になります。
特に近年はハラスメントに対する意識も高まり、言葉の選び方ひとつに気を使わなければなりません。
「教育よりも、自分の仕事に集中したい」と思う人が多いのも無理はありません。
将来の保証はない
「頑張って管理職を続ければ安泰」という神話は、すでに崩れています。
リストラや早期退職、役職定年など、会社は最後まで責任を持ってはくれません。
「頑張った先に何があるのか?」が見えないため、あえて管理職を目指さない人が増えているのです。
管理職と非管理職のリアルな違い
ここで、私の実感も踏まえて整理してみます。
| 項目 | 管理職 | 非管理職 |
|---|---|---|
| 裁量権 | 大きい(人事・予算・方針に関与できる) | 与えられた仕事の範囲内 |
| 責任 | 部署全体の成果や部下の行動も背負う | 個人の成果のみ |
| 報酬 | 手当や昇給あり(ただし増加幅は限定的) | 大きな変動は少ない |
| 働き方 | 会議・調整が多く時間が奪われやすい | 専門職として集中できる |
| 評価 | チームの数字・部下の成長で判断される | 個人のパフォーマンスで評価 |
| 休日 | 呼び出し・連絡対応あり | 比較的休みやすい |
この比較表を見ると、管理職は「権限と報酬」を得る一方で「責任と自由のなさ」を背負う立場だとわかります。
私自身の管理職経験:よかったこと
ここからは、私が実際に管理職をして感じたことを具体的に書いてみます。
裁量権が広がった
非管理職の頃は「与えられた仕事をどうこなすか」だけでした。
管理職になると「どの人にどんな仕事を任せるか」「チームの方向性をどう決めるか」まで考える必要が出てきます。
その分、自分の判断がチームの働きやすさに直結する。
部下に自由度を与え、成果につながったときや、成長を感じたときは、大きなやりがいを感じました。
認められる喜び
管理職に任命されたこと自体が、会社から「信頼されている」という証でした。
「あなたに任せたい」と言われたときの達成感は、非管理職時代には得られなかったものです。
***関連記事***

報酬が上がった
率直に言えば、収入面は大きなプラスでした。
家計に余裕ができ、子どもの教育費や将来への貯蓄に回せたことは安心感につながりました。
私自身の管理職経験:悪かったこと
一方で、つらかった部分もたくさんあります。
責任の重圧
部下がクライアントに迷惑をかければ、まず責任を問われるのは管理職です。
「自分は防げなかったミスだったのか」と悩み、眠れない夜を過ごしたことなど何度経験したことか。
会議での叱責
成果が出ないと、上層部の会議で厳しい指摘を受けます。
自分の力不足を突きつけられる瞬間は、正直なところつらいものがありました。
聞きたくない情報も、管理職になると嫌でも耳にします。精神面でボロボロになり、やる気をそがれることもありました。
同じ役職の同僚は、夜眠れなくなり、求職を余儀なくされました。
上下の調整に疲れる
部下を守りたい気持ちと、上司に従わなければならない立場の板挟み。
「もっと現場を理解してほしい」と思っても、上層部の方針は変わらない。
結局、自分が間に立って擦り切れることが多かったです。
休日でも休んだ気がしない
休日でも「トラブルがあれば呼ばれるかも」「あの件、どう進めていったらいいだろう…」など考えが頭の中をめぐり、気持ちが休まりません。
旅行中もスマホが手放せず、家族から「せっかくの時間なのに」と言われたことが心に残っています。宿泊先にパソコンを持ち込み、メール返信をしている自分は「これで幸せなのだろうか」と思い、悲しくなることもありました。
管理職になるかどうかは「自分と周囲で十分に考えて決める」
こうした経験を通じて思うのは、管理職になるかどうかは「良い・悪い」で決めるものではないということです。
- チームを動かし、裁量を持って仕事をしたい人には向いている
- 専門職としてスキルを磨きたい人には非管理職の道もある
どちらを選んでもキャリアとしては正解です。
大事なのは「自分がどんな働き方をしたいか」「周囲の理解を得られるか」です。
いま、定年を見据えて感じること
定年が見えてきた今、振り返るとこう思います。
- 管理職を頑張ったからといって、会社が将来を保証してくれるわけではない
- 上司が最後まで自分を支えてくれるわけでもない
- 結局、自分のキャリアを作るのは自分自身
管理職を経験できたことは間違いなく財産です。
でもそれは「会社のため」ではなく、「自分自身の経験を積むため」だったのだと思っています。
ワーママだったことに後悔はしていませんが、管理職であることを正解だったと言えるか、正直自信はありません。正解とできるためには、組織風土はとても重要であると実感しています。
まとめ
- 管理職になりたくない人が増えている理由は、報酬の少なさ・ワークライフバランスの崩れ・板挟み・育成の負担・将来不安
- 管理職と非管理職には、裁量権・責任・評価・休日の自由度に大きな違いがある
- 管理職を経験して、私は「裁量の広さ・認められる喜び・収入アップ」を得たが、「責任・叱責・調整の難しさ・休めない日々」に悩んだ
- 最後に大切なのは、自分の価値観に合った選択をすること
管理職になることはゴールではありません。
どちらの道を選んでも、自分の人生を支えるのは自分です。
「納得できるキャリア」を築くことこそが、働く上で一番大事なのだと思います。