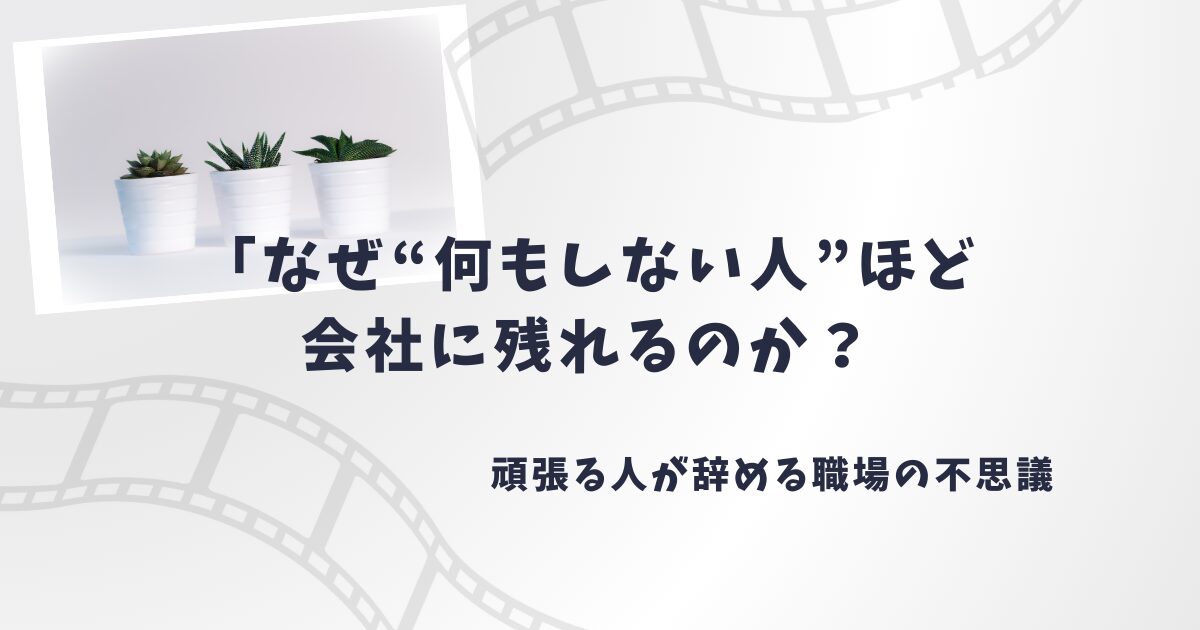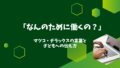目次
はじめに:誰もが見たことある「働かないのに居座る人」
会社で働いていると、一度は見たことがあるはずです。
「あまり仕事をしていないのに、なぜか会社に居続ける人」。
会議中も発言せず、仕事は他人任せ。締切を守らなくても怒られず、淡々と定時で帰る…。
一方で、真面目に一生懸命に頑張っている人ほど疲れ果てて辞めてしまう。
この「理不尽さ」にモヤモヤを抱えた経験がある人は多いのではないでしょうか。
この記事では、
- なぜ“何もしない人”が長く会社に残れるのか
- 逆に頑張る人が辞めやすい理由
- 実際の体験例
- そんな職場で自分を守る方法
を整理していきます。
そもそも「何もしない人」とは?
ここで言う“何もしない人”とは、怠けているのに気づかれずに済んでいる人のこと。
具体的には:
- 与えられた最低限の仕事しかやらない
- 自分から改善提案をしない
- トラブルが起きても「関わらない」姿勢をとる
- 上司には気に入られる
- 責任が重い仕事は避け、軽い仕事を選ぶ
表面上は大きな問題を起こさないため、目立たず、組織に居続けられるのです。
意図的なのか、もともと備わったスキル?なのか、、、わからない人もいます。
なぜ“何もしない人”でも残れるのか?5つの理由
ミスが少ないから
挑戦しない → 失敗しない → 怒られない。
「目立たない安全運転」で、逆に評価は下がらず残れてしまいます。
周囲が仕事を肩代わりしてくれるから
頑張り屋や責任感のある人が、結局フォローしてしまう。
結果的に「やらなくても仕事は回る」仕組みができてしまいます。
上司にとって扱いやすい存在だから
強い意見を言わず従順。
「波風立てない人」は、無難さゆえに上司から嫌われにくいのです。
評価基準が“結果”ではなく“在籍”だから
日本企業に多い「年功序列」や「在籍年数評価」では、成果がなくても居座れます。
本人が辞める気がないから
「辞める」と口にするのは、意外と真面目な人なのかもしれません。
“何もしない人”は不満も口にせず、「現状維持」でとどまり続けます。
***関連記事***

実際の体験例
体験例①:頼られすぎて辞めたAさん
以前、私の職場にAさんという女性がいました。
誰よりも責任感が強く、後輩の面倒も見て、上司からの信頼も厚い。
ところが、気づけば彼女にだけ業務が集中。周囲の“何もしない人”たちは、Aさんに仕事を振れば安心、という空気ができていました。
残業も休日出勤も当たり前。体調を崩し、ついにAさんは退職。
残ったのは、結局“何もしない人”ばかりだったのです。
体験例②:不思議と残り続けるBさん
また、別の会社ではBさんという男性がいました。
ほとんど仕事をせず、デスクに座っている時間の方が長い。
誰もが「どうしてこの人がまだいるんだろう」と不思議に思っていました。
でも彼は、上司に逆らわず、定時に帰り、ミスもしない。
結果、10年以上同じ部署に居続けました。人事異動もうまくかわしていたのでしょう。
その間に、バリバリ働いていた若手社員は何人も辞めていったのです。
頑張る人が辞めやすい理由
逆に「辞めるのはいつも頑張る人」。その背景には:
- 責任感が強く、抱え込みやすい
- 上司からの期待が大きすぎて燃え尽きる
- 「このままでは成長できない」と感じて転職を選ぶ
- 不公平さに耐えられない
という心理が働きます。
つまり、組織にとって本当に必要な人材ほど離れていきやすいのです。
「いい人ほど辞めるよね」という話を聞いたことは、必ずあると思います。
そんな職場で自分を守る方法
では、もしあなたが「頑張る人」側だった場合、どうすればいいのでしょうか?
頼まれごとを断る勇気を持つ
「全部引き受ける人」にならない。
「それは私の担当ではないですね」と線引きをすることが大切です。
成果を“見える化”する
頑張りが見えなければ評価されません。
数字や資料に残す、上司に報告するなど「伝える工夫」が必要です。
“ほどほど”の働き方を身につける
全力投球ではなく、力を抜くポイントを作る。
「やらない勇気」もまた、長く働くためのスキルです。
転職も一つの手段
「不公平さに耐える」より、「自分を正しく評価してくれる環境」に移る方が幸せな場合もあります。
何より組織の改革が必要
ここまで見てきたように、“何もしない人”が残り続け、頑張る人が辞めていくのは、 個人の問題ではなく組織の仕組みの問題 です。
評価制度の見直し
- 「長くいる」ことではなく「成果や貢献」を正しく評価する。
- 提案や改善に挑戦した人を高く評価する。
- チーム貢献(フォローや教育など目に見えにくい仕事)を評価に反映する。
負担の偏りをなくす仕組み
- 仕事を属人化させず、チーム全体で分担できる体制をつくる。
- 「気づいた人がやる」ではなく、業務フローに組み込む。
- 頼られすぎる人が一人で抱え込まないよう、リーダーが配慮する。
“沈黙する人”を放置しない
- 「問題を起こさないからいい」ではなく、貢献が見えない人には改善を促す。
- 面談やフィードバックを通じて役割を明確化する。
働きやすさと働きがいの両立
- 働きやすさだけがあると、“何もしない人”が温存される。
- 働きがいも感じられる環境を整えることで、優秀な人材が定着する。
まとめ:残る人=優秀な人、ではない
“何もしない人”が残り続けるのは、彼らが悪いのではなく、組織の仕組みがそうさせている部分も大きいのです。
そして、頑張る人ほど燃え尽きて辞めてしまうのも事実。
だからこそ、自分を守るためには「頑張りすぎない」「見せ方を工夫する」「時に環境を変える」ことが大切です。
理不尽な現実に気づいた今、あなたは「自分はどう働きたいか」を選ぶことができます。
頑張る人が報われる環境は、必ず存在するのです。