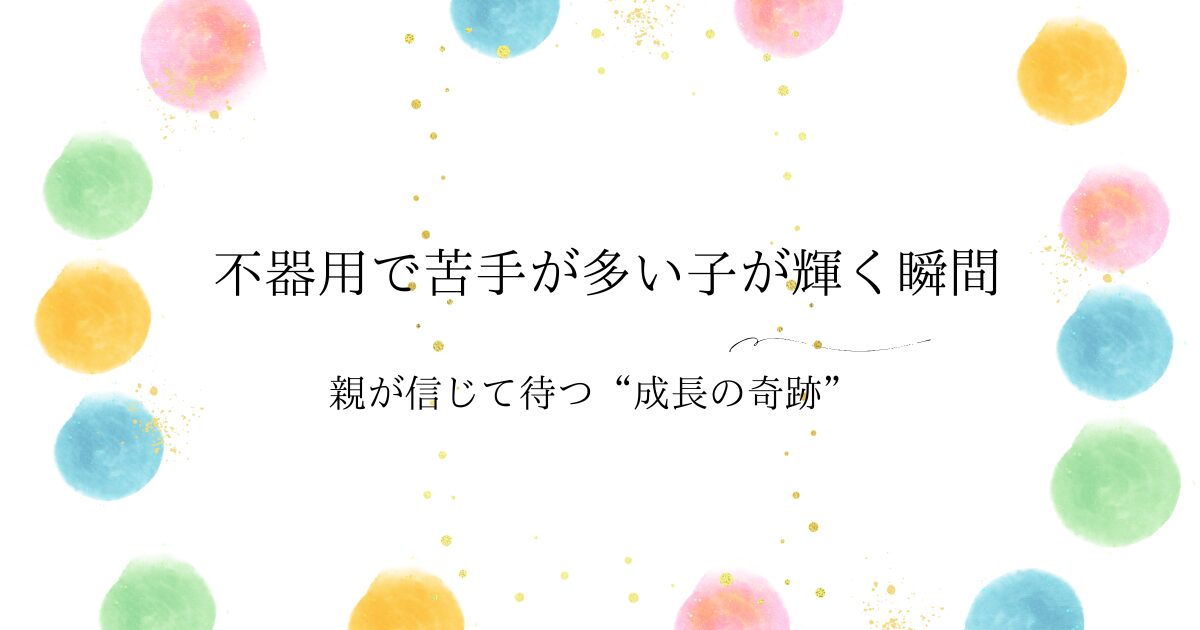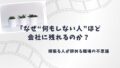目次
“子育て”のつらさは、いつの年齢でもある
子育てで一番つらい時期はいつか?という質問をネットで見ることがあります。体力的には0ヶ月から3ヶ月の新生児あたりが大変だった。1歳半から3歳頃のイヤイヤ期が辛かったなど、様々な意見を目にします。その年代で日々つらいことはたくさんあります。
私が親になって、どんな時がつらかったろうと考えたとき、「自分のことよりも、子どもが悩み苦しみ、悲しんでいるときが一番つらい」そう思いました。自分のことはいくらでも乗り越えることができるのですが、子どもたちのことでは、夜も眠れないことが何度となくありました。
特に、子どもが「うまくできない」「苦手が多い」「自分はダメな人間だ」など、様々なことで悩んでいる姿を見るとき、親は胸をえぐられるような気持ちになるのではないでしょうか。
私自身、娘が専門職を目指し進学したときに、今まで経験したこともない大きな壁にぶつかりました。
「器用に産んであげられなくてごめん」「もっと何でもこなせる子に、育ててあげられなくてごめん」――そう思わずにはいられませんでした。
ですが、その後娘は自分の力で立ち上がり、思いがけない成長を見せてくれました。
この記事では、親としての体験を交えながら、「苦手が多い子」「成長に時間がかかる子」がどう成長していくのか、そして親にできるサポート法についてお伝えします。
“子育て”で一番つらいことランキング
まず、多くの親が「子育てでつらい」と感じることを、ランキング形式で見てみましょう。
引用:ベネッセ教育総合研究所「子育て生活実態調査」2023年版より作成
| 順位 | 子育てでつらいこと | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 子どもの将来への不安 | 62% |
| 2位 | 自分の時間が持てない | 58% |
| 3位 | 子どもが言うことを聞かない | 52% |
| 4位 | 子どもの勉強や発達の遅れ | 48% |
| 5位 | 経済的な負担 | 45% |
| 6位 | 夫婦の育児方針の違い | 33% |
| 7位 | 孤独感・孤立感 | 28% |
この結果からも分かるように、**「子どもの成長や苦手分野」**は親にとって大きな悩みの種です。
私にとっても、まさにここが一番のつらさでした。子どもが、自信を失って悩んでいる姿を見るのは、本当につらいものです。
体験談:娘がつまずいた日々
娘は専門職に憧れて、自分の意思で進学先を決めました。彼女は中学卒業と同時に遠方の実業高校に通ったため、寮生活を送っていました。高校での経験を活かし、順風満帆な学生生活を夢見ていたのですが、、、。入学後、待っていたのは「苦手」「できない」「失敗」の連続でした。
自信をなくし、疲弊していく姿
- 実技試験でことごとく不合格
- 成績は下位から上がることができない
- 周囲が簡単にできることが出来ない
我が家は、自分で決めたことは簡単にやめてはいけないルールがあり、そう育ててきました。でも、入学して1年目の冬に「進級できないのでは」と悩んみ苦しみ疲弊している様子を見て、ついに私は初めて「もうやめてもいいよ」と口にしました。
それでもアパートに戻ると言い、駅まで娘を見送ったとき、必死に気持ちを奮い立たせて電車に乗り込む娘の顔を見て、涙が止まりませんでした。その時のことを思い出すと、今でも胸が熱くなります。
***関連記事***
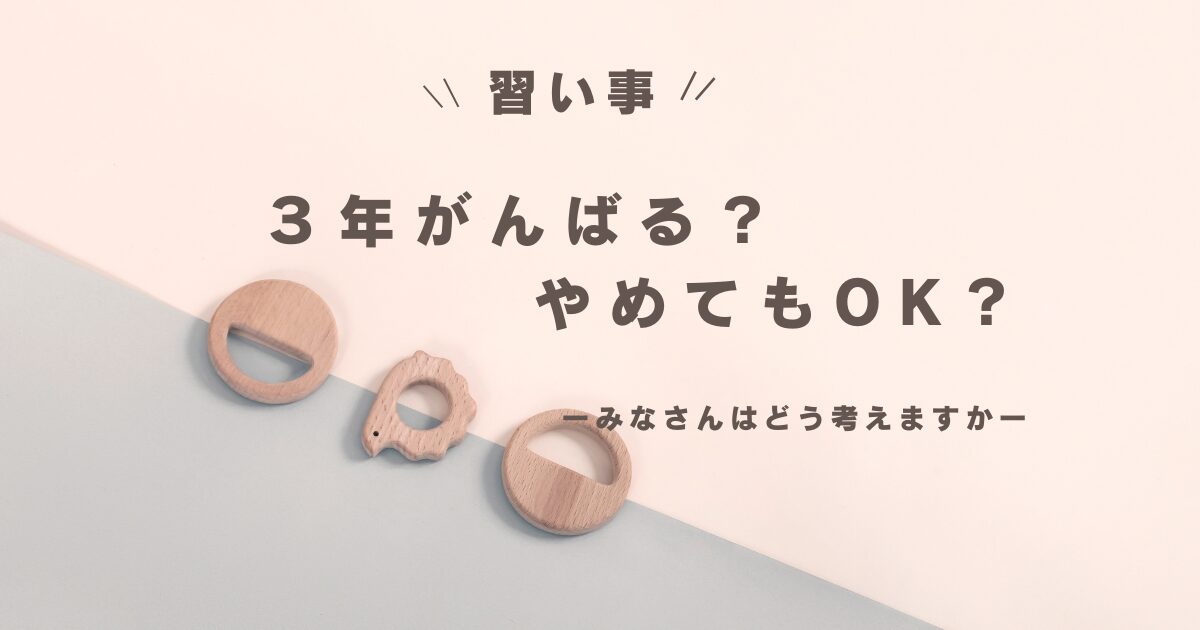
娘を救ったのは“自分自身”だった
ですが、その後の娘は、自分自身で立ち上がりました。何がきっかけだったのでしょう。親の言葉でもなく、友達に支えられたわけでもないのですが、別人になり必死で努力を重ねていったようです。
「不器用だから技術はすぐに身につかない。でも、知識なら積み重ねられる。それを武器にしよう!」そう考え、毎日ひたすら勉強を続けたようです。
- 苦手な実技は、すぐに上達しなくても知識で補う
- 一歩ずつ理解を積み重ねることで、自信を取り戻す
- 小さな達成感を原動力に、前へ進む
勉強も得意な方ではありませんでしたので、そんな考えになるなど正直驚きました。
時間はかかりましたが、少しずつ成果が見え始め、学校での成績が上がっていくにつれ元気を取り戻していきました。自信が彼女を変えてくれました。
その後、資格試験にも無事合格。第一希望の職場に就職することができました。
就職後も不器用さは変わらず、覚えるのに時間がかかり悩みもたくさんあったようです。それでも娘は、持ち前の明るさと粘り強さで、中堅職員として周囲に信頼してもらえるような立場にまで成長しました。
きっと、あきらめることなく、必死にもがいて努力した学生時代の経験が、娘を強くしてくれたのだと思います。苦手が多い子だからこそ、あきらめることなく、粘り強く続けられるようになったのだと信じています。
「苦手が多い子」に親ができるサポート法
ここで、私の体験から見えてきた「親ができるサポート法」をご紹介します。
「できたこと」を見逃さずに褒める
苦手が目立つ子ほど、褒められる経験が少なくなりがちです。
「昨日より早く準備できたね」「今日は自分から取り組めたね」と、小さな成長を具体的に言葉にして伝えることが大切です。
「継続すること」が大切だと伝える
苦手が多い子は、できるようになるまで時間がかかります。すぐに結果を求めず、地道に続けていくことが大切であることを繰り返し話してあげて下さい。
私は今も忘れられない言葉があります。「できる人間は、できない人間の気持ちがわからない。」これは、娘の部活動のコーチに言われた言葉です。
私はスポーツが得意で大きな大会にも何度か出場していました。なかなか上達しない娘を見ながら、心のどこかに「こんなことできて当たり前」「なぜできないの」という気持ちがあったのでしょう。心から反省しました。
この言葉で、「他人と比較せず、自分たちのペースで努力を続けて行こう」と気づくことができました。
サポートは“ほんの少し”で大丈夫!
全部を親が手伝うのではなく、背中をちょっと押す程度がちょうど良いです。
娘の場合も、送り出すときの声かけや、疲れて帰ったときの電話での励ましが支えになったと後で聞きました。
そして、理由があるのなら「やめてもいい」と言える余白を持つことも大切だと思いました。
親が一番怖いのは「子どもの夢を奪うこと」です。
けれども時には「やめてもいい」と伝えることが、子どもにとっての救いになる場合があります。
選び直す自由があると分かるだけで、子どもは踏ん張れるのです。
親自身も支えを持つ
子どもを見守るのは想像以上にエネルギーが必要です。これはどんな年齢でも同じです。
親が孤立してしまわないよう、家族で協力し合う、信頼できる人に話したり、地域の子育てサポートを利用することも大切です。
成長に時間がかかる子の強み
「成長に時間がかかる子」には、実は大きな強みがあります。
- 小さな努力を積み重ねる力
- 周囲への共感や優しさが育ちます
- 諦めずに続ける粘り強さ
娘を見ていても、器用さやスピードではなく、「人間としての深み」「人の痛みがわかる心」が育っていくのを感じました。
親としては「苦手」ばかりに目が行きがちですが、時間をかけて育つ力は、社会に出てから大きな武器になります。
***関連記事***

親として願うこと
私は、すでに亡くなった両親に手を合わせながら、子どもたちを見守ってほしいと毎日祈っています。
親になって感じたことは、「自分の幸せは、子どもが心身ともに健康であること」「子どもががんばっていると、自分も心穏やかに暮らしていける」――これは、子育てを通して心から実感したことです。
まとめ
「苦手が多い子」「成長に時間がかかる子」を育てるのは、ときにとてもつらいものです。
ですが、子どもは親が思う以上に強く、自分で乗り越える力を持っています。
親にできるのは、
- 小さな成長を認めて、どんな時も信じてあげる
- 他人と比較せずにおだやかに見守る
- 必要なときに、ほんの少しだけ支える
この3つを繰り返すこと。
私自身、いつも正しい親であったかと言われれば、失敗ばかりのダメな親でした。子どもたちに、親として人間として成長させてもらったと感謝しています。
時間はかかっても、子どもは必ず「思いがけない成長」を見せてくれる――私は体験を通して、そう確信しています。