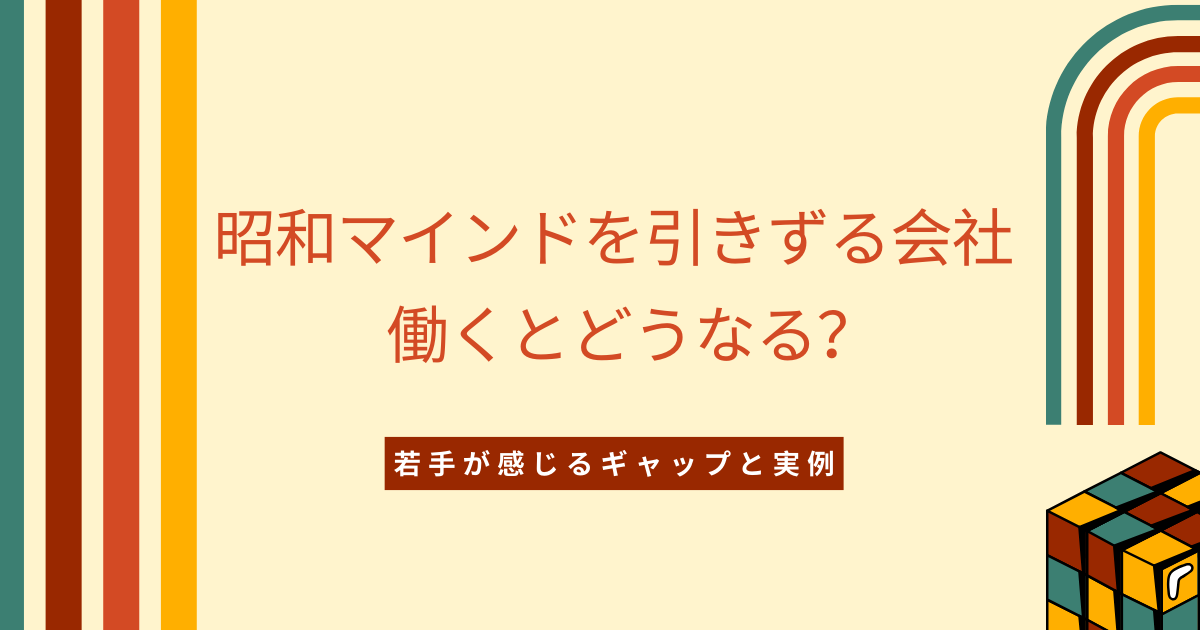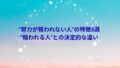目次
「昭和マインド」。
職場でよく耳にするようになった言葉ですが、皆さんの会社にも残っていませんか?
- 残業してこそ一人前
- 上司の言うことは絶対
- 飲み会で本音を語り合うのが仕事の一部
- 紙・電卓・ハンコが最強ツールである
…どれも昭和時代には“正解”だったかもしれません。
しかし、令和の職場では「効率が悪い」「時代遅れ」と感じられることも多く、世代間のギャップや働きづらさを生む原因になっています。もちろん、飲み会の強要は今ではパワハラ扱いです。
私は経理と人事の現場を経験してきましたが、まさに「昭和マインドが残る職場」と「令和マインドに進化した職場」の両方を見てきました。
その経験をもとに、今回は “昭和マインドが残るとどうなるか” を掘り下げていきます。
昭和マインドとは何か?
「昭和マインド」について、まずは整理してみましょう。
| 昭和マインドの特徴 | 具体例 |
|---|---|
| 残業が美徳 | 「昨日は終電まで頑張った」が自慢話になる |
| 上司絶対主義 | 「上がそう言っているから」の一言で決まる |
| 飲み会文化 | 断ると「ノリが悪い」と評価される |
| 根性論 | 「体調管理も仕事のうち」と熱で出勤を求める |
| 紙・電卓中心 | Excelより電卓、メールよりFAX |
このように「根性・従順・長時間労働・アナログツール」がセットで出てきます。
経理の現場で見た“切ない瞬間”
私が経理を担当していた頃、忘れられない光景があります。
【シーン1】:電卓カチャカチャ上司
- 上司:「よし、これで残高が合ったぞ!」(電卓を連打しながら満足そう)
- 私:「…SUM関数なら一瞬なんだけどな(心の声)」「残高間違ってるし…」「言いにくいな」
私も昭和生まれですが、IT好きな自分とのギャップを痛感しました。「ITなんて信用できない」「苦手意識が強いからなあ」(逃げ腰)の言葉は日常茶飯事です。
“一生懸命さ”は伝わるけど、時間のロスが大きすぎて切ない…。
若手社員はさらにショックを受けていました。
「このまま職場で働き続けても成長できないのでは」と悩んでいたようで、相談を受けたこともあります。
人事の現場で感じた“時代錯誤”
人事の様子をみて、こんな場面も目の当たりにしました。
【シーン2】:寿退社が当たり前?
あるベテラン上司が、中堅の女性に言った一言。
「結婚したら辞めたりするのかな? その時は、早めに教えてね」
…令和の時代にですよ。
その場の空気が凍ったのを、今でも覚えています。
その女性は「私はキャリアを積みたいです」と返しましたが、
こうした“古い常識”が残っていると、モチベーションを下げる原因になります。
昭和マインドが残るとどうなるか?
ここで図解してみましょう👇
【図解】昭和マインドの悪影響
- ❌ 若手が辞める → 「古すぎてついていけない」
- ❌ 生産性が下がる → 手作業・残業が増える
- ❌ イノベーションが止まる → 新しい提案が通らない
- ❌ 心理的安全性が欠ける → 意見を言えない雰囲気
結果として、 「会社の未来を担う人材」が育たない・残らない という深刻な課題につながります。
「いい昭和」「残すべき昭和」もある
ここまで昭和マインドを批判的に語りましたが、実はすべてが悪いわけではありません。
むしろ「今の職場に必要」と思うものもあります。
| 残すべき“いい昭和” | 変えるべき“古い昭和” |
|---|---|
| 仲間意識・助け合い | 長時間労働の美徳化 |
| 責任感・やりきる姿勢 | 飲み会強制参加 |
| 数字や仕事への誠実さ | 「女性は補助的役割」的な価値観 |
いい部分は残しつつ、不要な部分は手放す。
この見極めが大切です。
世代間のモヤモヤを可視化してみる
実際の職場では、世代ごとにこんな“モヤモヤ”が発生しています。
| 世代 | モヤモヤポイント |
|---|---|
| 若手社員 | 「なぜ紙?」「なぜ残業自慢?」 |
| 中堅社員 | 「効率化したいのに上司に止められる」 |
| 上司 | 「若手が根性なしに見える」「新しいやり方が怖い」 |
こうして並べると、「どの世代も実は不満を抱えている」ことが分かります。
だからこそ、歩み寄りが必要なのです。
令和型へのアップデート方法
ではどうすればいいのか? 経理×人事の経験から見たポイントは以下の通りです。
- ITを味方につける
- 経理はクラウド会計、人事はオンライン人事システムを導入
- 「人がやる」より「システムがやる」仕組みを整える
- 上司にプライドを傷つけないような方法でITを教え込んでいく
- ルールを明文化する
- 飲み会は自由参加
- 育休・時短は誰でも使える権利として整備
- 昭和マインドを“美談”にしない
- 「昔はこうだった」より「今はこうできる」を評価する
- 世代間で学び合う場をつくる
- 若手からITを学ぶ
- ベテランから交渉術や現場感覚を学ぶ
まとめ:電卓上司も若手も進化できる職場に
電卓をカチャカチャ叩く上司を見て切なくなった私ですが、「数字に誠実に向き合う」という姿勢そのものは学ぶべき点がありました。
結局のところ、昭和マインドは“全部捨てるもの”ではない。
- 無駄な部分は削ぎ落とし
- 良い部分は残す
そのうえで「令和マインド」と融合することが、これからの職場には欠かせません。
昭和と令和のハイブリッドな職場こそ、若手もベテランも居心地よく、成長できる環境だと思います。