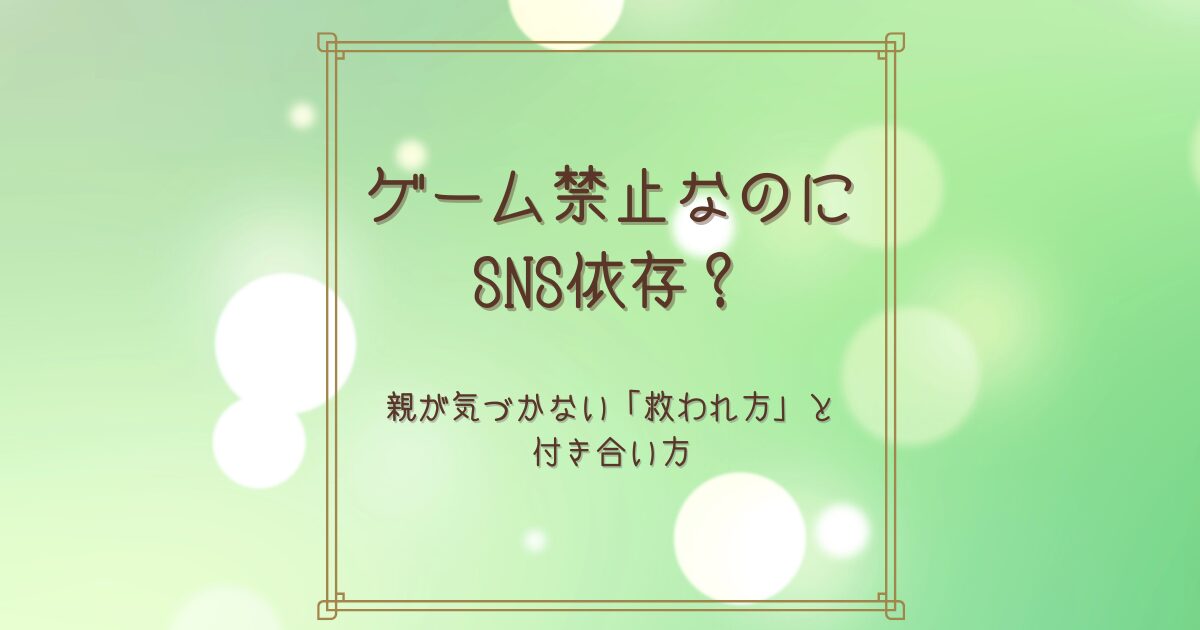目次
この記事は、「SNS=悪」でも「SNS=正義」でもない、そのあいだの“グレーな場所”にいる私たち親へ問いかける内容です。
デジタルに振り回されるのではなく、デジタルを味方にして生きる。
それが、今を生きる親の新しい形なのだと思います。
SNSが溢れている世界の親の姿
「いつまでスマホ見てるの?」「ゲームは1日30分!」
子どもにはそう言いながら、気づけば自分もスマホ片手にSNSを開いている——。
夜、子どもが寝静まったあと、インスタで流れてくる家族の投稿や、X(旧Twitter)で見かける、同じような悩みをもつ多くの人を見て、自分だけじゃないんだとホッとする瞬間。
SNSで救われたことが、何度あっただろう。
一方で、「こんなにスマホを見てる私はダメな親かも」と、罪悪感が押し寄せることも。
でも、その“矛盾”の中にこそ、今の時代のリアルな「親の姿」があるのかもしれません。
子どものゲームと親のSNS、実は“同じ構造”
「子どもはゲーム、親はSNS」――
対象は違っても、根っこにある心理は驚くほど似ています。
| 見る/遊ぶ目的 | 子どものゲーム | 親のSNS |
|---|---|---|
| 感情の動き | ワクワク・達成感・逃避 | 安心・共感・癒し |
| 使用タイミング | 暇なとき・友達との話題 | 家事の合間・夜のひとり時間 |
| 効果 | ストレス解消・自尊心回復 | 安心感・気分転換・孤独の緩和 |
つまり、
「ゲームに夢中になる子」と「SNSを眺める親」は、同じ人間的欲求の表れ。
“現実のストレスから少し離れて、心を軽くしたい”という気持ちの表現なのです。
***ルールを決めるのはどうでしょう***

SNSがくれるのは「答え」ではなく「共感」
SNSの中には、たくさんの情報があります。
子育てのノウハウ、発達の専門家の発信、時短レシピ、そして日々の小さな笑い。
けれど、私が救われたのは「情報」ではなく、「共感」でした。
たとえば、
- 子どもが宿題をやらずに悩んでいる投稿
- 仕事と家庭の両立に悩むつぶやき
- 「今日は何もできなかった」と正直に書かれた日記
それらを見るたびに、「私だけじゃない」と思える。
その安心感が、心の負担をそっと軽くしてくれます。
SNSを“悪者”ではありません
ニュースでは「SNS依存」「スマホ育児の弊害」といった言葉が並びます。
確かに、依存や誹謗中傷などの問題は現実にあります。
でも、すべてのSNSが悪ではありません。
SNSを通じて誰かの体験を知り、孤独を和らげ、笑い合えることもある。
それはもう、「悪影響」とは言い切れない“つながり”の力です。
私たちは、デジタルをどう使うかを選ぶ自由を持っています。
そして、その選び方こそが、親としての“新しい感性”なのだと思います。
デジタルとの距離を「ゼロか百」で考えない
私たちはつい、
デジタルとの関わり方を「使う=悪」「使わない=正しい」
と、白黒で分けてしまいがちです。
けれど実際の生活は、そんなに単純ではありません。
🪞使い方次第で「救い」にも「負担」にもなる
SNSもゲームも、使い方次第。
たとえば、
疲れた夜にふと見た子育て動画で、「うちも同じだ」とホッとしたり、Xで同じ悩みを抱える人の投稿に共感したり。
そんな“つながり”が、心を支えてくれることがあります。
🧩「距離を取ること」より大切なのは、“自分にとって心地いい距離”
完全に遮断してしまうと、
「みんな頑張ってるのに自分だけダメかも」と孤立を感じてしまうことも。
だから大事なのは、デジタルを遠ざけることではなく、
“自分にとって心地いい距離感を見つけること”。
デジタルを「敵」ではなく「ツール」として見直す。
1日中スマホを触らない日があってもいいし、気分転換に1時間SNSを眺めるのも悪くない。
⚖️「ゼロか百」ではなく、「ちょうどいい中間」を探す
親も子どもも、
少しずつその“ちょうどいい中間”を探していけばいいのではないでしょうか。
そう考えると、
SNSを通じて誰かの優しさや知恵に触れた経験も、ちゃんと意味のある時間になります。
🌱デジタルと上手に付き合うことが、これからの“育ち方”
デジタルを遠ざけすぎず、でも溺れすぎず。
そのバランスこそが、今の時代の“新しい育ち方”であり“親の生き方”なのかもしれません。
「子どもがSNSばかり」でも、それは「親の背中」を見ている
子どもは、親が思っている以上に“見ています”。
親がスマホを片手に誰かに共感したり、SNSを通じて気持ちを整理していたりする姿も、
子どもはちゃんと感じ取っています。
「スマホ=悪」と決めつけず、
「どう使うと前向きになれるか」を一緒に考えること。
それが、本当の“デジタル教育”かもしれません。
デジタルの中にも、ちゃんと「ぬくもり」はある
SNSの向こう側には、人がいます。
それを忘れなければ、デジタルの世界も怖くありません。
コメントのやり取り、DMでの励まし、「いいね」のひとつにも、“誰かがあなたを見ている”という温度があります。
実際に会うことができなくても、心の距離は、画面を超えて近づくことがある。
それを知っているからこそ、私たちは今日もスマホを開くのかもしれません。
「SNSに救われた」経験を、否定しなくていい
SNSやYouTubeを見て救われた瞬間があるなら、
それはあなたが「人の優しさを受け取れる力」を持っている証拠。
「子どもには厳しいのに、自分はスマホばかり」そんな罪悪感を抱える必要はありません。
SNSの中で誰かの想いに共感し、笑ったり泣いたりできること。
それは、ちゃんと生きる力になっています。
親も“バランスの練習”をしている途中
子どもがゲームに夢中になるように、
親もSNSに助けられながら、日々を乗り切っている。
それは決して矛盾ではなく、「今を生きる親」の自然な姿です。
デジタルを使いこなすことより、デジタルに流されずに“自分を保つ力”を育てていけばいい。
完璧でなくていい。
私たちも子どもと一緒に、デジタルとのちょうどいい距離を探していけばいいのです。
最後に│ママたちへのエール
SNSの中には、たしかに情報の洪水もあります。
でもその中に、「あなたはひとりじゃない」と伝えてくれる言葉も、確かにあります。
スマホの向こう側にある“つながり”を、上手にすくい取れる自分でいたい。
そして、子どもにもこう伝えたいのです。
「使い方さえ間違えなければ、SNSは“味方”になるよ」と。