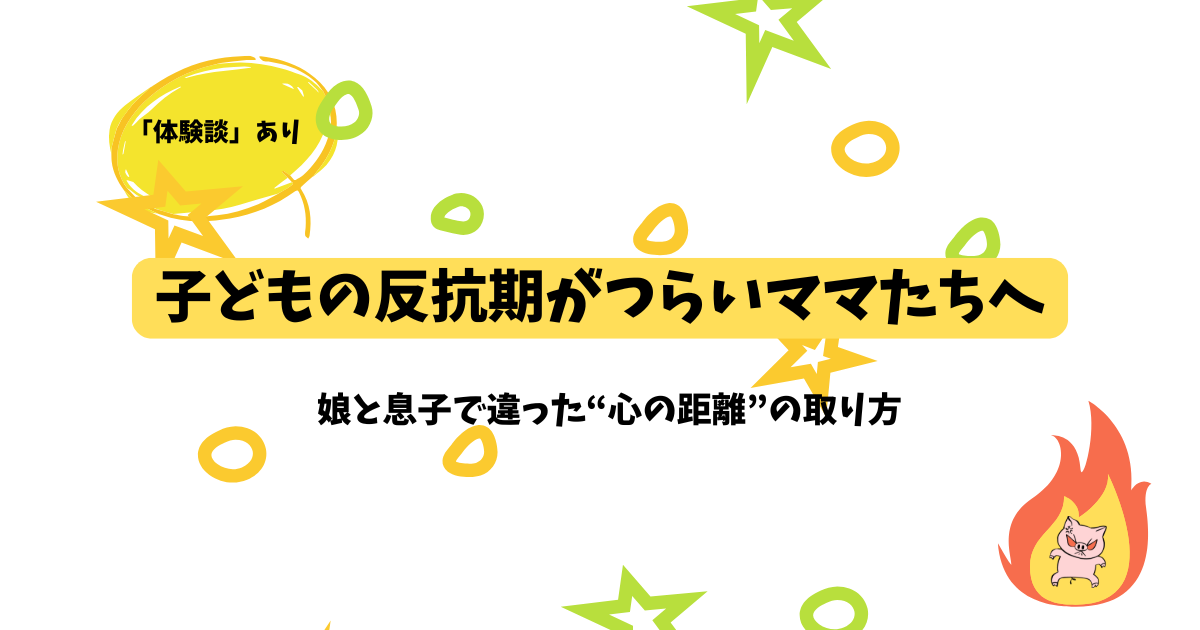目次
「子どもの反抗期」という言葉を聞くだけで、胸が重くなる親は多いものです。
小さな頃は素直だった子が、急に口をきかなくなり、目も合わせなくなる。
そんな態度に戸惑い、傷つき、どう接していいのかわからなくなる瞬間があります。
私は娘と息子の2人を育てましたが、まったく違うタイプの反抗期を経験しました。
「反抗期」とひとことで言っても、男女差や年齢による違いが大きいもの。
そして何より、親自身のメンタルをどう保つかが最大のポイントだと感じています。
娘の「反抗期」―― 話さない・怒る・全部親のせい
娘の反抗期が始まったのは中学1年のころ。
それまで何でも話してくれていた子が、ある日を境に**「話しかけても返事がない」**。
こちらが何か言うと、「うるさい」「もうわかってる!」と怒鳴られる日々でした。
忘れもしないのは、学校でのトラブルがあった日のこと。
心配して声をかけたら、
「お母さんがうるさいから余計に疲れる!」と怒鳴られ、私も怒鳴り返すという負のループ。
反抗期というより、女同士のケンカじゃないかと思う激しさでした。物が宙を舞うようなことも、正直。
何を言っても反発され、**“何も言わないほうが正解”**なのかと悩む日々。
正直、私の方が精神的に追い詰められていました。
そんな娘も、高校入学と同時に寮生活となり、家から離れたことで少しずつ変わっていきました。
親元を離れ、自分で生活を管理する大変さを経験したことで、
「お母さん、あのとき言ってたこと、今わかった気がする」と言ってくれたのです。
反抗期は、親にとって“試練のトンネル”のようなもの。
けれど、子どもがそのトンネルを抜けたとき、ようやく親の言葉の意味を理解できるのかもしれません。
***高校進学を決めるときも悩みの連続でした***

息子には「反抗期」がなかった?――静かな思春期の形
息子の場合は、娘と対照的でした。
「反抗期」というような激しい態度はなく、いつも淡々としていました。
もともと口数の少ない子でしたが、中学時代も、特に口答えをすることはなく、言われたことをこなすタイプ。正直、「これでいいのかな?」と戸惑うこともありました。
世間では「反抗期がない子は危ない」「親に気を使っているだけ」など、いろいろな意見を耳にします。でも私は今になって思います。
反抗の形は人それぞれ。
怒鳴ったり無視したりすることだけが「反抗期」ではないのです。
息子なりに、親と距離を取りながら、自分で考えて行動する力を身につけていったのだと思います。
📊男女別:反抗期の傾向と違い
| 性別 | 主な反応の特徴 | 親が意識したいこと |
|---|---|---|
| 女の子 | 言葉・態度で強く反発。感情の起伏が大きく、母親と衝突しやすい。 | 言葉を真に受けず、感情が落ち着くのを待つ。距離を取る勇気も大切。 |
| 男の子 | 無言・無視など“静かな反抗”。親に甘える気持ちを隠す。 | 「構いすぎない」「短く話す」「存在を見守る」が鍵。 |
| 共通 | 自立と依存の間で揺れる時期。 | 親の安定した態度が、心の安全基地になる。 |
娘と息子、どちらにも共通して言えるのは、
「自分で考えたい」「干渉されたくない」という気持ちが根底にあること。
親が一歩引いて見守る姿勢こそ、子どもが安心して成長できる土台になります。
***こんなことも原因になります***

親の心が疲れる理由
反抗期のつらさは、子どもよりも親のほうが消耗してしまうことにあります。
どんなに頑張っても否定され、優しく話しても「うざい」と言われる。
まるで努力が裏目に出るような日々。
「うちの子だけこんなにひどいの?」「私の育て方が悪かったの?」
そう責めてしまう親は少なくありません。
でも、反抗期とは「親離れ・子離れ」の自然なプロセス。
子どもが安心して自立できるようになるための“心のリハーサル期間”です。
そう思うと、少し気持ちが楽になります。
📊年齢別:反抗期の特徴と親の対応ポイント
| 年齢・時期 | 主な特徴 | 親の対応ポイント |
|---|---|---|
| 幼児期(2〜4歳) | 「イヤイヤ期」。思い通りにしたい。 | 気持ちを受け止めて選択肢を与える。 |
| 小学生(高学年) | 自立心が芽生え、言い返す。 | 「どう思う?」と考えさせる。 |
| 中学生 | 感情が爆発。親を否定する言動も。 | 感情的にならず、距離を置いて見守る。 |
| 高校生 | ストレスや進路で不安定に。 | 会話より「信頼しているよ」と表現する。 |
| 大学生〜社会人初期 | 親との距離を再構築する時期。 | 干渉より“信頼”を重視する。 |
反抗期の形やタイミングは家庭によって違います。
表を見て「うちはこの時期なのかな」と客観的に整理するだけでも、親の心が少し落ち着くものです。
親のメンタルを守るためにできること
感情的になったら「一度離れる」
反抗的な態度にカッとなるのは自然なことですが、そのまま言い返してしまうと関係が悪化します。
そんなときは、物理的に距離を取る勇気が大切です。
「今日はお互い落ち着いてから話そう」と伝えるだけで十分です。
「理解されない」と感じたら、言葉を減らす
子どもは言葉よりも“態度”を見ています。
どんなに正論を言っても、感情がこもっていれば伝わりません。
無理に説得せず、あえて静かに見守ることで、「信頼されている」と感じる子も多いのです。
自分を責めない
反抗期に疲れきった親の多くが、「私のせい」と思い込んでいます。
でも、反抗期は成長過程の一部であり、「うまくいかないのが普通」。
少し距離を取って、自分の趣味や仕事、友人関係に意識を向けてみましょう。
親が笑顔でいることが、何よりのサポートです。
距離ができたら、再構築のチャンス
娘が寮生活に入って数か月後、「お母さん、あのとき心配してくれてたんだね」と言ってくれた瞬間、
私は心の中で泣きました。
あの距離があったからこそ、親のありがたみを実感できたのだと思います。
距離は「終わり」ではなく、「成長の始まり」。
それを信じて、少し待つ勇気を持ちましょう。
兄弟の関係性が変わったことで親に対する態度も変わっていった
娘と息子は6歳離れています。
幼いころはあまり関わりがなく、娘が中学生の頃までは、むしろ「うるさい弟」と扱っていました。
けれど、高校生になってからは変化が。
弟の頑張りや優しさに気づき、「うちの自慢の弟」と言うようになったのです。
兄弟の関係もまた、反抗期を経て成熟していきます。
親が焦らず見守ることで、家族のバランスが自然に整っていくのを感じました。
まとめ――反抗期は「親子の信頼を再構築する時間」
反抗期は、子どもが「自分で生きる力」を試す時期です。
そして親にとっては、「信じて見守る力」を試される時期。
娘と息子の反抗期を通して感じたのは、どんな形でも、最後には親の愛情が届くということ。
怒っても、無視されても、心の奥では親の存在を感じています。
だからこそ、焦らず、比べず、「親も成長の途中」と思って、少し肩の力を抜いていきましょう。