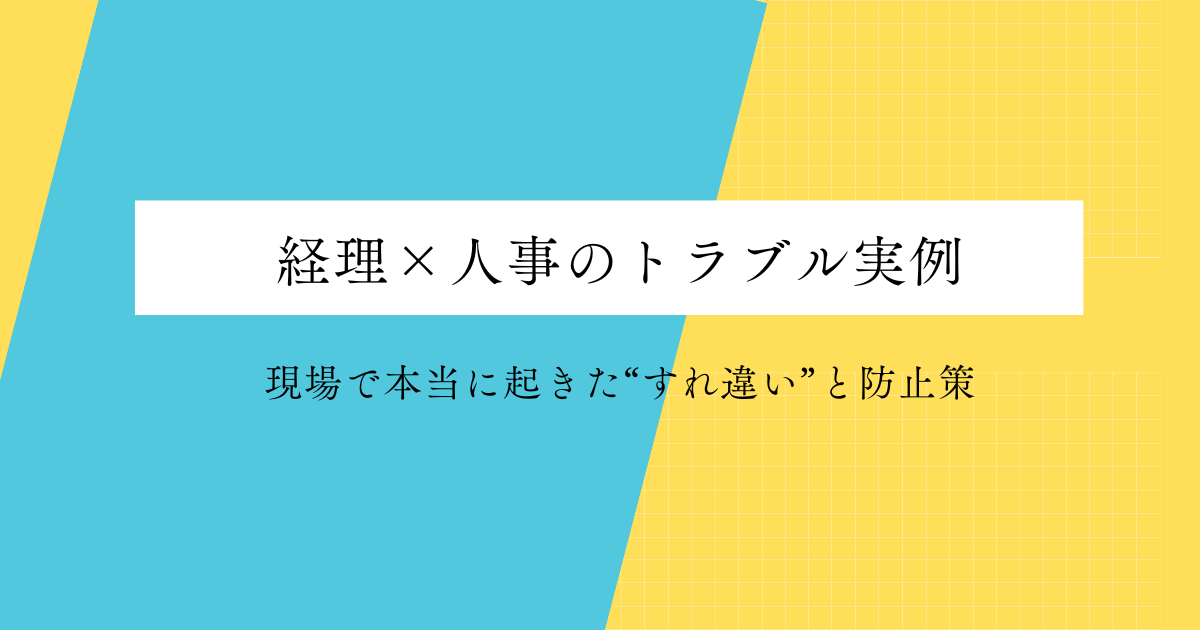目次
経理と人事の連携不足で起きるトラブルを5つの事例で解説しています。給与計算や入退社、経費精算など、現場でよくある“すれ違い”の原因と防止策をまとめています。
私もトラブル解決のために奔走する毎日です。なぜうまくいかないのか、考えてみました。
■ 導入:経理と人事の「すれ違い」はどこでも起きている
経理と人事。どちらも会社を支える管理部門でありながら、日々の仕事の中では「ちょっとしたすれ違い」が絶えません。
たとえば――
- 「勤怠の締めが遅れて、給与計算がギリギリ」
- 「退職処理が経理に伝わらず、翌月も給与が発生してしまった」
- 「経費の勘定科目をめぐって意見が割れる」
どの職場にも起こり得る、経理×人事の“ズレ”の数々。
実際に両部門を経験した立場から言うと、トラブルの多くは「コミュニケーション不足」や「責任範囲の曖昧さ」から生まれています。
【図表①】経理と人事の業務フローの違い
| 部門 | 主な業務 | 優先すること | 時期的なピーク |
|---|---|---|---|
| 人事 | 勤怠管理、採用、社会保険、労務対応 | 従業員対応・スピード感 | 月初〜月中(勤怠確定〜給与データ作成) |
| 経理 | 仕訳、支払、決算、税務処理 | 数字の正確性・締め処理 | 月末〜翌月初(支払・月次決算対応) |
人事は「人」に寄り添う仕事、経理は「数字」に寄り添う仕事。
その違いが、良くも悪くも職場での“ズレ”につながります。
***関連記事***
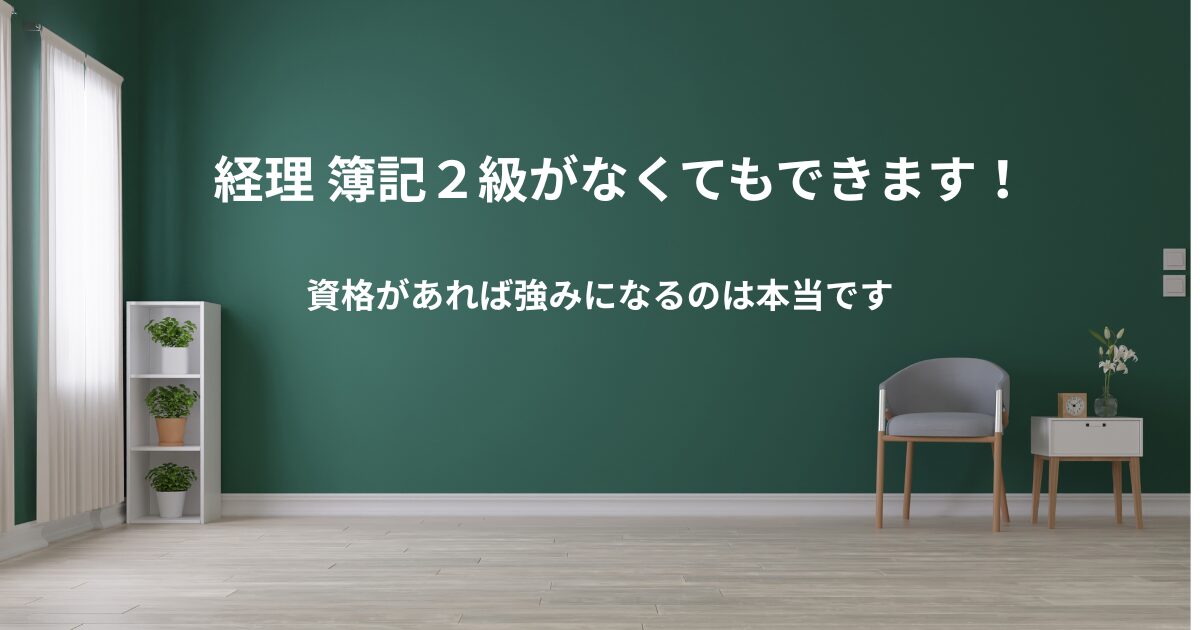
事例①:給与計算の認識ズレ
最も多いのが、給与データの確定タイミングのズレ。
人事が「勤怠をもう少し確認したい」と思っても、経理は「締め処理が遅れる」と焦る。
結果、ミスや修正が発生します。
よくあるケース:
- 打刻漏れを後から修正 → 再計算が必要
- 時給変更が反映されていない → 源泉徴収や社会保険料に影響
防止策:
- 「勤怠確定日」「給与データ提出期限」を明文化
- 修正ルールを決め、「当月分」「翌月調整」を区別
ちょっとしたルール化だけで、月末のバタバタは大幅に減ります。
事例②:入退社情報の連携ミス
人事が退職届を受け取っても、経理に伝わらないまま給与データを作成してしまう。
結果、退職者に給与が誤って支給されるという痛いミスも。
よくある原因:
- 情報共有がメールのみ
- 入退社チェックリストが紙ベース
- 担当者不在時の引き継ぎ漏れ
防止策:
- 「入退社報告フォーム」を作り、経理・人事・上司で共有
- チャットツールで「退職確定通知」を自動送信
- 退職処理を“経理側でも確認”する二重チェック体制
事例③:経費精算ルールの認識違い
人事が福利厚生として支給した費用を、経理が「交際費扱い」と判断して修正依頼。
こうした勘定科目の食い違いもよくあります。
よくある対立:
- 「社員懇親会費は福利厚生?」
- 「お祝い金は給与扱い?」
経理は「税務上の扱い」、人事は「社員への配慮」を重視するため、視点がずれるのです。
防止策:
- 勘定科目ガイドラインを共有(例:福利厚生費・交際費・給与の区分)
- 年1回、経理・人事合同の勉強会を実施
- 新ルールは社内ポータルで更新・通知
事例④:年末調整・社会保険対応の責任範囲
年末調整の時期、人事と経理が「どこまで確認するか」で揉めることもよくあります。
たとえば扶養控除申告書や保険料控除証明書の不備。
ありがちなすれ違い:
- 人事「内容チェックは経理でお願いします」
- 経理「人事が確認してから渡してほしい」
防止策:
- 年末調整の全体フローを「業務分担表」で明示
- 不備発見時の“戻しルート”を明確化
- 申告書チェックリストを共有
年末調整は「一部でも抜けると全体が崩れる」業務。
属人化を防ぐ仕組みが命です。
事例⑤:勤怠システムと会計システムの連携不備
最近増えているのが、システム間の自動連携ミス。
勤怠→給与→会計がシームレスに動かないと、結局手入力や二重チェックが発生します。
よくあるトラブル:
- 勤怠システムで休暇修正後、給与計算に反映されていない
- RPAが動かずデータが欠落
- システム更新でCSV形式が変わり、インポートエラー
防止策:
- 定期的な照合ルーチンを設定(例:毎月20日)
- 自動化任せにせず、人が“確認するポイント”を固定化
- RPA・API連携も「監査対象」として運用ルールに明記
【表①】トラブル原因と防止策まとめ
| トラブル内容 | 主な原因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 給与計算のズレ | 締め日・確定日が不明確 | 日程の明文化+修正ルール化 |
| 入退社情報の伝達漏れ | メール・紙ベース連携 | 共通フォーム+自動通知 |
| 経費精算の科目食い違い | 税務・感覚のギャップ | 勘定科目ガイドライン共有 |
| 年末調整の責任範囲 | チェック体制の曖昧さ | 分担表+チェックリスト |
| システム連携不備 | 自動化依存・更新ミス | 定期照合+監査運用ルール |
経理と人事の“間”をつなぐ人の重要性
経理も人事も「正しいこと」をしているつもりなのに、噛み合わない。
その溝を埋めるには、“両方の言葉がわかる人”が必要です。
たとえば、
- 人事側から経理視点を理解する人
- 経理側から現場の働き方を理解する人
どちらの立場にも寄り添える「橋渡し役」がいるだけで、業務効率も雰囲気も大きく変わります。
現場で本当に機能している会社ほど、
「人事と経理の打ち合わせが“会議”ではなく“対話”になっている」ものです。
まとめ:連携は「性格の相性」ではなく「仕組み」で解決
経理と人事のトラブルは、人間関係の問題ではなく“仕組みの問題”です。
感覚の違いを個人のせいにせず、「どんなルールがあれば再発しないか」を話し合うことが大切。
どちらの部署も、最終的には「会社と社員を守る」という同じ目的を持っています。
互いの視点を尊重し合い、「経理にも、人事にもやさしい仕組みづくり」こそが、
本当の意味での“管理部門の連携”です。