目次
回転寿司チェーン「くら寿司」での迷惑行為動画が拡散され、大きな社会問題となっています。
一瞬の“ノリ”や“ウケ狙い”が、取り返しのつかない事態へ発展してしまう——。
SNSが日常化した今、これは他人事ではありません。
人物特定、住所や親の勤務先など、ありとあらゆる情報が拡散されていて、見たくなくても飛び込んでくる今の時代に、親として苦しさを覚えます。
この事件は、単なる「若者のいたずら」ではなく、子どもの心の教育と家庭の在り方が問われた象徴的な出来事だと考えます。
この事件から何を学び、どう子どもに伝えていけばよいのでしょうか。私なりの親としての考え方をお話ししていきます。
迷惑行為の裏にある「承認欲求」と「現実とのズレ」
SNSには、“誰でも発信者になれる自由”があります。
しかし同時に、現実とネットの境界があいまいになる危うさも潜んでいます。
子どもたちの心理背景
- 「いいね」やフォロワーの数で、自分の価値を測る
- 「注目されたい」という欲求が、正しい判断を上回る
- 周囲が止めない環境の中で、“悪ふざけ”がエスカレートする
子どもたちは悪意があったわけではなく、「ウケること」や「話題になること」が正義だと誤解してしまうのです。
しかしSNSの世界は、笑って済まない“現実”と地続きです。
やってしまった後に待っている「現実」
ネット上の迷惑行為は、あっという間に拡散し、本人だけでなく家族まで巻き込みます。
待っているのは…
- 学校や進学先での処分、退学、内定取り消し
- 顔や名前の特定、誹謗中傷、将来への影響
- 店舗や企業からの損害賠償請求
かつての「悪ふざけ」は、SNS社会では**“社会的制裁”**につながります。
そして、一度ネットに出た情報は一生残る。
つまり「消せない後悔」になるのです。
親として子どもに教えるべき3つのこと
ここでは、親が家庭で意識したい3つの指導ポイントを整理します。
成長してからでは遅いのです。幼少期から、自然と教えていくことが大切です。
🟦【図解】親が教えるべき3つの力(ちから)
| 力(ちから)の名前 | 内容 | 実践例 |
|---|---|---|
| 判断力 | 「これはやっていいか」を考える力 | 投稿前に「誰が見ても大丈夫?」と声かけ |
| 共感力 | 相手の気持ちを想像できる力 | 「これをされたらどう思う?」と話す |
| 責任感 | 自分の行動に責任をもつ力 | 家のルールを一緒に決める・守る |
「見られる」意識を育てる
ネットは家の中の遊び場ではなく、“世界中に公開される場所”です。
「誰が見るかわからない」「一度出したら消せない」——この感覚を、日常の中で少しずつ教えていくことが大切です。
実践法:
- 家族でニュースを見て、「もし自分が映っていたら?」と話し合う
- 親自身が投稿する際は、「これ、誰が見てもOKかな」とつぶやく
→ 子どもは、親の“考える姿勢”を通して学びます。
「叱られた経験」を奪わない
最近は「叱ると傷つく」「機嫌を取った方が早い」と考える親も増えています。
しかし、間違いを正してくれる存在がいない子どもは、社会でブレーキをかけられません。
「叱る=否定」ではなく、「叱る=守りたい」というメッセージ。
親が“嫌われ役”になる勇気こそ、子どもの将来を守る最大の愛情です。
「見せる背中」が最大の教育
子どもは親の言葉よりも、親の行動を見ています。
- SNSで他人を笑いものにしていないか
- 店員さんへの態度はどうか
- 家で感情的な言葉を吐いていないか
人の見ていないところでどう行動するか。それが、子どもが真似る“生き方”です。
【体験談】:娘が友人に笑われ疑問に思ったこと
娘が高校時代、友人とファミレスに行ったときのことです。会計が終わり、店員さんに「ごちそうさまでした」と言ったときに、友人に笑われたそうです。
「なんで、こっちが客なのにあいさつするの。変なの。」
我が家は、小さい頃から当たり前のように、店をでる際はごちそうさまと言って帰りました。確かにお金を払っているのだから、当然のサービスを受けているのかもしれません。
でも、気持ちよく食事ができ、楽しい時間を提供してくれるお店の方への感謝の気持ちをもつのは、ごく自然のことだと考えています。
子どもたちは、その親の気持ちを理解しているのか、成人した現在も「ごちそうさまでした」と言って店をでます。私はその気持ちを忘れてほしくないと思っています。
幼少期からの関わりが「判断力」を育てる
子どもが問題行動を起こす背景には、幼少期からの“自己コントロール力の不足”が関係しています。
小さいころからの関わりが、SNS時代を生き抜く判断力の基盤になります。
🟩【年齢別】親の関わり方と指導ポイント
| 年齢 | 教えたい力 | 関わり方の例 |
|---|---|---|
| 幼児期 | 善悪の基準 | 「それをされたら悲しいね」と共感で伝える |
| 小学校低学年 | 感情の言語化 | 「怒った時、どうすればいいかな?」と考えさせる |
| 小学校高学年 | 他者への影響理解 | 「あなたの一言で誰かが傷つくこともあるよ」と話す |
| 中高生 | 自立と責任 | スマホ利用ルールを“話し合い”で決める |
禁止ではなく、**「一緒に考える姿勢」**が大切です。
親が答えを押しつけず、子ども自身が「自分の行動の意味」を理解できるように導きましょう。
家庭の在り方が社会を変える
くら寿司の事件は、家庭の一つの問題に見えて、実は社会全体の教育の鏡です。
どんな学校教育よりも、最初に“人としての土台”を築くのは家庭です。
親ができることは、完璧な子育てではなく、「間違いをそのままにしない姿勢」。
日々の会話の中で、「あなたの行動には意味がある」「他人を思いやることがあなたを守る」と伝えていくことです。
🟨【家庭チェックリスト】親ができる5つの習慣
| チェック項目 | できている? |
|---|---|
| ニュースやSNS話題を家族で共有している | □ |
| 子どもの投稿や動画に一言アドバイスをしている | □ |
| 「叱る=愛情」として、理由を言葉で説明している | □ |
| 自分のSNS利用や言葉遣いを意識している | □ |
| 「あなたの行動はどう影響する?」と対話をしている | □ |
この5つを意識するだけで、家庭の雰囲気は大きく変わります。
「うちは大丈夫」と思わず、日常の会話の中に教育を織り込むことが、子どもを守る最善策です。
ネット社会で育つ子どもたちへ
これからの時代を生きる子どもたちは、ネットから避けては通れません。
「情報に触れる速さ」よりも「情報を扱う力」が求められます。
SNSを否定するのではなく、どう付き合うかをしっかりと教える時代。
親が正しい姿を見せ、誠実に生きることが、何よりの教育です。
家庭の中でのひとつの言葉、ひとつの態度が、子どもの価値観を形づくります。
くら寿司の事件を「他人事」で終わらせず、わが家はどう関わるか」と立ち止まることこそ、社会を変える第一歩です。
***関連記事:SNSはゼロではありません***
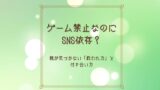
まとめ|“見守る”だけでは育たない
くら寿司の迷惑行為は、子どもの未熟さと、社会の教育不足が交錯した結果です。
親ができることは、「叱る勇気」と「見せる背中」。
そして、子どもと一緒に考える時間を持つことです。
ネット社会の中で、
「優しさ」「責任」「思いやり」を家庭で育てる——。
それが、次の世代を守るもっとも確かな方法なのかもしれません。


