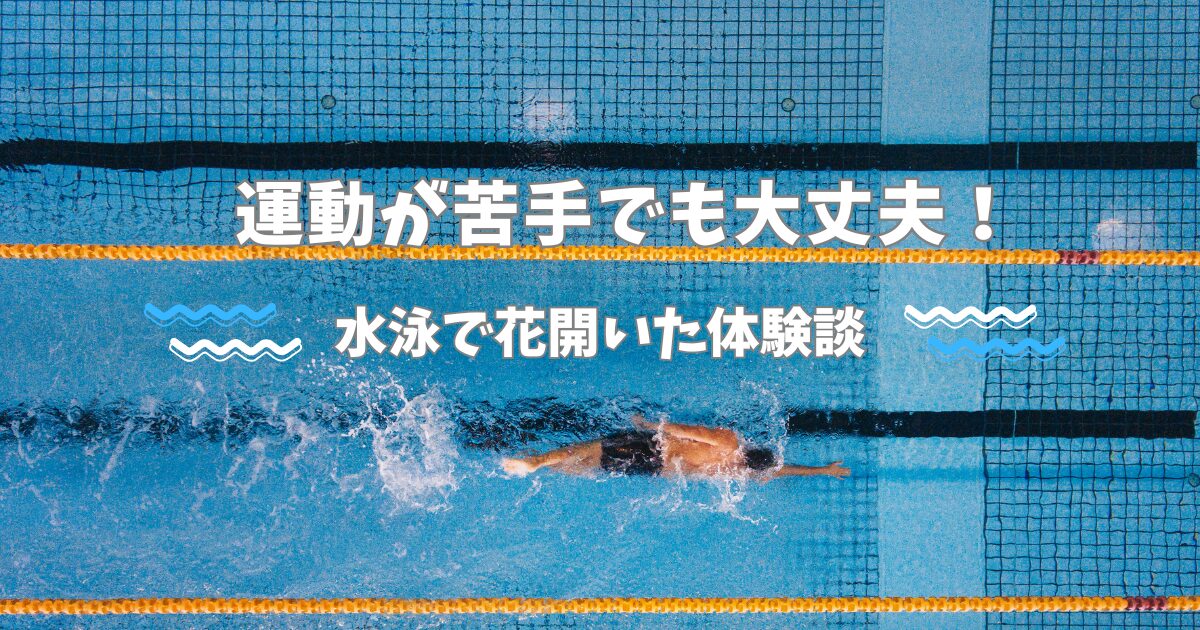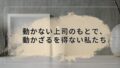目次
「うちの子、どうしてこんなに運動が苦手なの?」
運動会のかけっこでいつも遅くて悲しくなる。
ボールを投げても、全然飛ばないし、変な方向へばっかり。
そんなわが子を見て「うちの子、運動神経が悪いのかも」と心配するママは少なくありません。
「サッカーや野球など、チーム競技でキラキラ輝いて、注目の的になっている子がうらやましい」そんなことを何度思ったことでしょう。
実は、“運動音痴”には遺伝的な要素と環境的な要素の両方が関係しているようです。
でも、それは「一生苦手なまま」という意味ではありません。
むしろ、親の関わり方しだいで大きく伸びる可能性があります。
この記事では、医学的な研究データと、私自身の息子の体験をまじえながら、「運動が苦手な子に、親ができること」をやさしくお伝えします。
「運動音痴」が大化けすることも、本当にあるんですよ。
運動音痴は遺伝?医学的な根拠から見る真実
子どもの運動能力について、文部科学省や筑波大学などの研究では、
「運動神経は半分が遺伝、半分が環境で決まる」と報告されています。
| 要因 | 内容 | 参考研究 |
|---|---|---|
| 遺伝的要素 | 筋肉の質や反射速度、バランス能力などはある程度遺伝 | 文部科学省 国立スポーツ科学センター「運動能力の遺伝的要因研究」 |
| 環境的要素 | 幼児期の運動経験や家庭での遊び方が強く影響 | 筑波大学 体育系研究「発育発達期の運動経験と運動能力の関連」 |
| モチベーション | 成功体験が運動意欲を高める | 大阪教育大学「小児期における運動の心理的影響」 |
つまり、遺伝による差はあっても、**「どんな環境で育つか」**が決定的に大きいのです。
運動神経は母親からの遺伝って本当なの?
ネットなどで、「運動神経は母親からの遺伝が大きい」という記事を目にすることがあります。
こんな落ち込む記事を目にして、心配なママもいることでしょう。
我が家に限っては、まったく当てはまりませんでした! 逆パターンではありますが、、、。
私は「運動だけ」は人並み以上にでき、全国大会にも何度か出場しています。それも、球技です。
我が家の子どもたちは、二人とも球技はあまり得意ではありませんでした。ですから、母親の遺伝は関係ないと考えています。
息子の体験|球技が壊滅的だった少年が変わった瞬間
息子は、典型的な“運動音痴”だったと思います。
何をやっても形にならず、走ればぎこちない、ボールを投げれば肩を使えず、今一つ恰好が悪い。
逆上がりも何度練習してもなかなかできず、息子自身も「自分は運動が苦手なんだ」と思い込むようになっていました。
内心、どうすればいいのか分からず、「運動は向いてないのかも」とあきらめかけていました。
そんなとき耳にしたのが——
「水泳・スキー・陸上は、運動神経にあまり左右されないらしいよ」
という言葉でした。
息子は以前から興味を持っていた、スイミングスクールに入会。
最初の頃は“泳いでいるのか、おぼれているのか”という状態でした。
それでも不思議と楽しそうで、毎回「今日も行く!」と自分から出かけていきました。
やがて、コーチから意欲だけを買われたのでしょう。育成コースへの誘いを受け、本人もやる気に火がつきました。
なかなかタイムは伸びず、同じ年の子よりずっと遅い時期が長く続きましたが、家族みんなでサポートして練習していくうちに、自分の得意な泳ぎを見つけ、少しずつフォームが整い泳ぎが軽やかに。
5年生のころから成績が少しずつ伸びはじめ、
中学生では都道府県大会優勝、全国を意識できる記録を出すまでに成長しました。
このことで自信がつき、おとなしかった息子が、学校生活でも積極的になっていきます。
成人した今でも、球技はあまり得意ではありませんが、水泳とスキーでは、「本当に同じ子?」と思うほど動きが美しくなりました。
***関連記事:自信は子どもを成長させます***

医学的に見た「運動が苦手な子」が伸びる理由
- 繰り返しの運動刺激が脳神経を発達させる
幼少期に体を動かすことで、小脳や前頭葉の神経回路が強化される(筑波大学・脳科学研究)。
つまり、「運動が苦手でも、続ければ脳が変化する」のです。 - 成功体験が「運動の快感」を記憶する
「できた!」という瞬間に、脳の報酬系が活性化します。
これがモチベーションにつながり、継続する力になります。 - 多様な運動経験が基礎力を育てる
バランス遊び、なわとび、鬼ごっこなど、
いろいろな動きを経験することで運動の“土台”が整います。
***関連記事:子どもは変わっていきます***
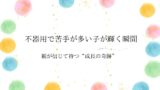
幼稚園児へのサポート|「遊びがいちばんのトレーニング」
幼児期は、「上手にできるか」よりも「体を動かす楽しさ」が大切。
| 目的 | サポート方法 | ママのポイント |
|---|---|---|
| 体を動かす習慣をつける | 鬼ごっこ・すべり台・ケンケンパ | 遊びの中で自然に身体能力を育てる |
| バランス感覚を養う | 丸太渡り・平均台・石跳び | 転んでも笑って終われる雰囲気づくり |
| 成功体験を重ねる | 「できたね!」と褒める | 結果より“挑戦した勇気”を評価する |
💬 声かけのコツ
「うまくできなくても、がんばったのがすごいね」
「失敗も次へのステップ。今日はここまでできたね!」
この時期は、神経系が最も発達する“黄金期”。
家の中でゴロゴロ遊んだり、公園で走ったりするだけでも、
十分に運動神経の基礎づくりになります。
小学生へのサポート|「得意の芽を見逃さない」
小学生になると、周囲と比べて落ち込むことも増えます。
そんなとき、親が“得意のタネ”を見つけてあげることが大切です。
| 目的 | サポート方法 | ママのポイント |
|---|---|---|
| 苦手の中にも楽しみを見つける | 球技が苦手なら水泳・陸上・スキーなど | 「できるかも」と思える分野を探す |
| 自主的な練習習慣をつける | 一緒にジョギング・ストレッチ | “一緒にやる”ことで続けやすく |
| 成長を見える化する | 記録ノート・写真・動画 | 子どもが「できるようになった!」を実感できるように |
💬 ママの一言が、子どもの背中を押す
「昨日より上手になったね」
「努力してる姿、ちゃんと見てるよ」
「苦手」より「がんばってるね」に目を向けると、
子どもは自信を取り戻し、少しずつ体を動かすことを楽しめるようになります。
親がやってはいけない3つのこと
- 「運動音痴」と決めつけること
→ 子どもが「どうせ自分はダメ」と思い込む原因に。 - 得意な子と比べること
→ 比較はモチベーションを下げます。「昨日の自分」と比べる習慣を。 - 焦って習い事を詰め込むこと
→ 苦手克服よりも、「好き」を育てる方が効果的。
成長のタイミングは、必ずやってくる
息子が、水泳で本当に成績が伸びてきたのは、小学6年生ころからです。
「遅咲き」でもいいんです。
大切なのは、その子なりのペースで続けること。
運動音痴は「才能の欠如」ではなく、「経験の積み重ねと環境」でいくらでも変わります。
ママが焦らず、
「今日もがんばったね」と声をかけてあげること。
それが、子どもの心と体を動かすいちばんのエネルギーです。
苦手な子ほど、「できた!」の喜びを一番大きく感じられる。
それが運動神経よりもずっと大切な力。
まとめ|ママのまなざしが、子どもの運動神経を育てる
運動が苦手な子を支えるコツは、「できない」を責めず、「できた」を一緒に喜ぶこと。
結果が出ないと、親も子も落ち込むことはあります。そんな時でも前向きに、次のステップに向かって一緒に進んで行くことが大切です。
子どもは、ママが見てくれているという安心感の中で、何度でも挑戦できるようになります。
今日も、「失敗してもいいよ」と笑って声をかけてあげてください。
その一言が、未来の“運動好きな子”を育てる第一歩です。
参考文献
- 文部科学省 国立スポーツ科学センター(2020)「運動能力の遺伝的要因研究」
- 筑波大学 体育系(2020)「発育発達期の運動経験と運動能力の関連」
- 大阪教育大学(2019)「小児期における運動の心理的影響」
- 日本小児科学会(2021)「運動発達と神経発達の関連」