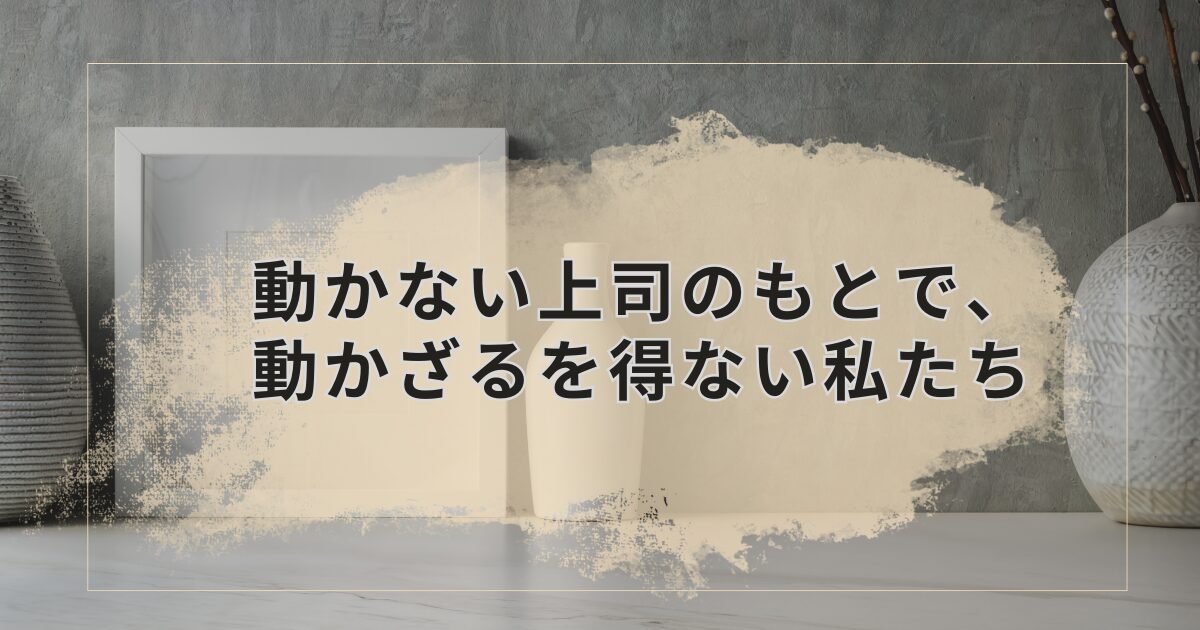目次
「上司が指示しない」職場の混乱
経理の仕事は、期限と正確さが命。
毎月決まった締めや支払い、決算期など、ルーティンが多い一方で、突然のトラブル対応も多い。そんな職場に必要なのは、段取りを整理して指示を出せるリーダーです。
ところが私がかつて勤めていた職場には、「マネジメントができない上司」がいました。
決めてほしい事項があっても、何度も催促しないと返事はなし。挙句の果てに、大切なメール返信を忘れている。部内の業務改善を訴えても、自分の考えに固執して、一向に向上しない部署を作り上げている。
周囲の部下は信頼できない上司に、陰口の嵐となり、空気感は最悪の職場でした。

その上司はすぐに顔に出るタイプで、いらついているのがすぐわかります。周りのみんなに嫌な思いをさせないよう、別室で質問をするように心掛けていました。
「どうすればいいですか?」に答えない上司
たとえば、月初の支払い処理。
私は「この請求書、どちらの科目で処理しますか?」と尋ねても、「うーん、どうだろうね。前はどうしてた?」と返ってくる。
仕訳の基準を決めてほしいのに、判断を避ける。
仕方なく自分で過去データを調べ、同じ処理をしておくと、後から「ここ、違うからやり直して」と言われる。
――だったら最初に言ってほしい。
けれど上司は、部下に指示を出すことに極端に慎重で、「自分の指示で間違うのが怖い」ようでした。
結局、誰もが自己判断で仕事を進め、結果としてミスが増える。
経理は数字の世界。曖昧さが許されないのに、上司が舵を取らないことで、現場は常に不安定でした。
***関連記事***
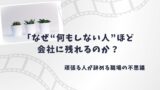
「放置」されるチームの疲弊
放置型の上司の特徴は、「何もしないことが悪いことだと気づかない」点です。
本人は「任せている」「信頼している」と思っている場合もあります。
でも実際は、現場を放置して責任を回避しているだけ。
部下からすれば、判断のたびに不安になり、確認のたびにストレスを感じる。
特に経理は「責任の所在」がはっきりしないと怖い仕事。
間違えば取引先にも影響が出るし、決算では会社全体の数字に関わります。
私の部署では、次第にみんなが「余計なことは言わない」「自分の身を守る」方向に変わっていきました。
報告しても上司は動かない。ならば自分で完結させるしかない。
チームとしての一体感はなくなり、ただ“無難にやり過ごす”日々が続きました。
「上司が指示できない方がいい」なんてことはない
一部では、「放任型の上司のほうが自由に仕事ができていい」という声もあります。
でも、それは部下のスキルが高く、組織が成熟している場合に限ります。
経験の浅い社員や、判断に会社方針が絡む仕事では、
「何を」「どこまで」「いつまでに」やるかを明確にするのがマネジメントの基本。
指示がないということは、方向性を失うということです。
経理では、「上司が指示できない=リスク管理ができない」と同義です。
締めが遅れ、監査対応が後手になり、経営判断も遅れる。
現場だけでなく、会社全体に影響します。
「上司が指示しない方が楽」というのは、一見自由に見えて、実は“放置されている状態”。
部下の成長も、組織の信頼も生まれません。
「放置上司」の下で働くときの現実的な対処法
では、そんな上司の下で働くとき、どうすれば自分を守れるのでしょうか。
私が実践してきた、現実的な対処法を紹介します。
指示待ちではなく、「提案型」に変える
「どうしますか?」ではなく、「A案とB案がありますが、Aで進めてよろしいですか?」と聞く。
選択肢を提示すれば、上司も答えやすくなります。
また、後から「そんなつもりじゃなかった」と言われても、「確認済み」として記録を残せます。
放置型上司は決断を避ける傾向があるので、
**“Yes/Noで答えられる形で持っていく”**のがポイントです。
メールや議事録で「エビデンス」を残す
口頭確認だけでは、後から「言った・言わない」になるのが定番。
特に経理では、メールで残すことが何よりの防御になります。
打ち合わせ後には簡単な議事録を送り、
「本日の決定事項として〇〇を進めます」と書いておく。
証拠を残すことで、上司が曖昧な指示を出しても、自分を守れる環境をつくれます。
「頼れる同僚」ネットワークをつくる
放置上司の下では、チームよりも個人戦になりがちです。
でも、一人で抱え込むとメンタルがすり減ります。
同僚同士で「この件どうしてる?」と情報交換できる関係をつくるだけで、仕事の正確さも安心感も変わります。
私は同じ課の先輩と「判断に迷うリスト」を共有し、毎週確認するようにしていました。
結果的に、部署全体の精度も上がりました。
「直属上司」だけを見ない
上司が機能していないなら、他部署の信頼できる人を巻き込むのも方法です。
たとえば、経理の上位部署(財務部や経営企画部)に相談し、「方向性を確認したい」と伝えると、正式な方針が下りることもあります。
“上司が機能していないこと”を個人の問題にせず、
「組織としてのリスク」として扱う視点を持つことが大切です。
「自分のキャリア」を切り離して考える
放置上司の下では、学びが止まることがあります。
誰も教えてくれず、仕事も単調。
そんなときは、「この環境で何を得るか」を自分で設定すること。
たとえば、
- 手順書を自作して、仕組みを整える経験を積む
- チームを巻き込む練習をする
- 次に行く職場で通用するスキルを磨く
「この上司の下にいる時間=自分の修行期間」と捉えると、気持ちが少し楽になります。
環境を変えたくなったら、それは次のステップのサインです。
マネジメントできない上司を見て学んだこと
正直、当時は「どうしてこんな人が上司なのか」と思っていました。
でも今振り返ると、学んだことも多かった。
それは、「人を動かすことは、能力ではなく“責任感”の問題」だということです。
部下を動かす責任を負う覚悟がない人は、どんなに知識があってもマネージャーにはなれません。
だからこそ、私は後輩を指導するとき、
「自分が楽になるためではなく、相手が動きやすいように伝える」を意識するようになりました。
マネジメントできない上司を反面教師にして、
自分がどんな上司になりたいかを考えるきっかけになったのです。
まとめ|「上司を変える」は難しい。でも「自分を守る」はできる
マネジメントができない上司は、どこの職場にもいます。
経理のようにミスが許されない現場では、その影響が大きく、「何をどう進めればいいのか」見えなくなることもあります。
けれど、上司を変えることはできません。
できるのは、「自分の働き方」と「関わり方」を変えること。
- 提案型で動く
- 記録を残す
- 仲間をつくる
- 上司以外のルートを確保する
それだけで、同じ環境でも息苦しさは確実に減ります。
放置上司の下で学んだのは、
「マネジメントされなくても、自分をマネジメントできる人になる」こと。
それが、どんな職場でも生き抜く力になるのだと思います。