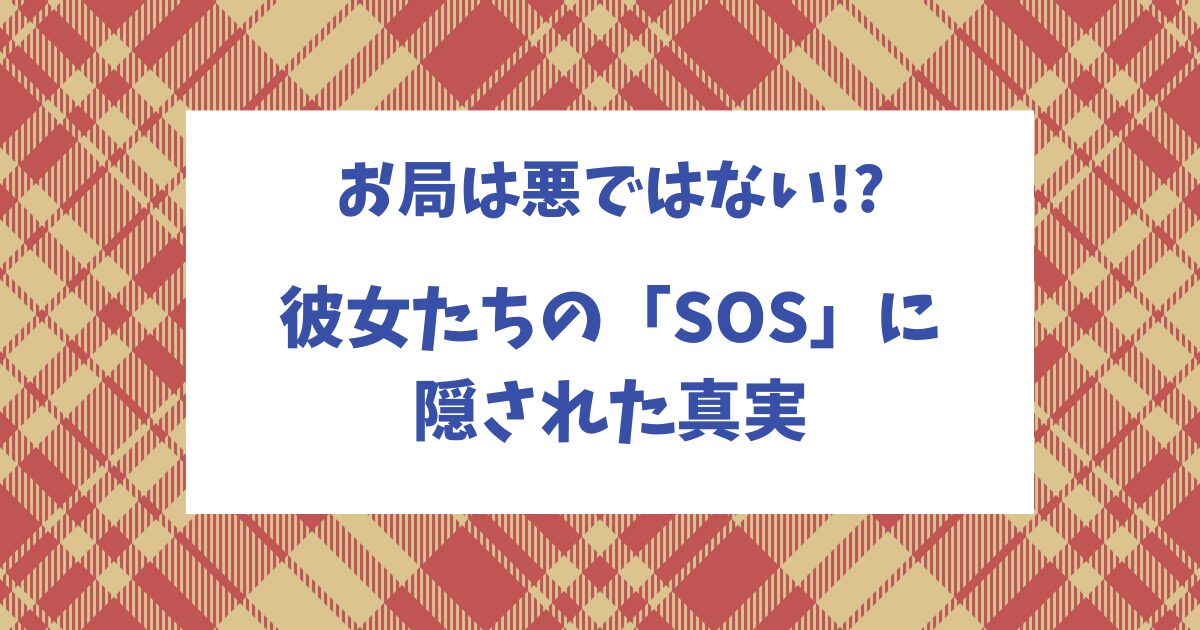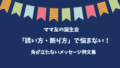目次
職場で理不尽な小言や無視に遭うと、「あの人、性格が悪いんだな」と切り捨てたくなりますよね。特に、長く会社にいるベテラン社員(いわゆる「お局」)から受けるストレスは、仕事へのモチベーションを大きく下げます。
前回の記事では、理不尽な態度が「無くなった」体験をお伝えしましたが、今回は視点をガラッと変えます。なぜ、彼女たちはそんな態度を取らざるを得ないのか? 彼女たちの行動は、実は**「不安」や「満たされない思い」**から来る、必死の「助けて!」というサインかもしれません。
本記事では、彼女たちの行動をただ責めるのではなく、人間の心と会社の仕組みという二つの視点から分析します。私たちは、彼女たちの態度が**「心理的な欠落」を満たすための行動であり、同時に「会社の構造的な失敗」**が作り出した産物であると考えます。この「裏側」を知ることで、あなたは彼女たちの言動に感情的に振り回されなくなり、自分の心をラクにする方法を見つけられるはずです。
「前回の記事」

第1章:立場を失うことへの「見えない恐怖」
長年会社に尽くしてきたにもかかわらず、なぜか理不尽な態度を取ってしまう彼女たちの心には、「私はもう必要とされていないのでは?」という、見えない恐怖が潜んでいます。この不安こそが、彼女たちを頑なにし、攻撃的にしてしまうのです。
「昔のやり方」にこだわるのはなぜ?:知識が古くなるのが怖い
人は、**「自分は役に立っている」**と感じ、他者から認められることで自信を持ちます。しかし、会社の業務やシステムがデジタル化で急速に変化する現代において、**長年かけて身につけた「経験」**が、新しいシステムや常識の前では通用しなくなるスピードは速いものです。
- 無力感への防御: 彼女たちが何十年もかけて築いた「専門性」が、新しいやり方によって一瞬で古びてしまう。これは、自分の存在価値を否定されたような感覚になります。
- 変化を拒否するプライド: 新しいスキルを学ぶことは、新入社員と同じスタートラインに立つことを意味します。プライドの高い人にとって、これは屈辱です。だからこそ、「このやり方で何十年もうまくいってきた」「昔はこうじゃなかった」と頑なに主張することで、かろうじて保たれた自分の「専門家」としての居場所を守ろうとしているのです。新しいものを否定することで、自分の価値を相対的に守ろうとするのです。
職場で「母親役」をしたがるのはなぜ?:承認欲求のねじれ
会社が生活の中心になっている人にとって、職場は家と同じくらい大切な場所です。そのため、彼女たちは自分の**「居場所」を強固なものにするために、後輩に対して「親」や「管理者」のような過剰な介入**をしてしまうことがあります。
- 過剰な「おせっかい」の裏側: 後輩の仕事に口を出し、細かすぎる指導をするのは、**「私がいないとあなたはダメだ」「私はあなたにとってなくてはならない存在だ」という自己確認作業です。これは、本来、仕事の成果や新しい貢献で満たされるべき「承認欲求」が満たされないために、「支配」**という形でねじれて現れているのです。
- 境界線への執着: プライベートや時間を大切にするワーキングママが増える中で、「仕事が全て」としてきた彼女たちの働き方の価値観が揺らぎます。自分の価値観が否定されることへの防衛反応として、**「私が決めたルール」**を押し付け、相手を攻撃してしまうのです。
態度が大きいのは「自信がない」証拠?
威圧的で理不尽な態度を取る人ほど、実は心の底に強い不安を抱えていることが多いものです。本当に自信がある人は、穏やかで冷静な態度で他者を導く余裕があります。
- 「支配」で不安を隠す: 相手を威圧したり、無視したりすることで、「私はこの場の力関係の頂点にいる」という感覚を得ようとします。これは、自分の内心の不安定さを、権威の誇示によって一時的に解消しようとする行為です。
- 放置で悪化する: マネージャーや上司が「面倒だから関わるのをやめよう」と問題行動を放置すると、「この態度で自分の立場は守られる」と彼女たちに誤解を与え、支配欲や攻撃性は組織によって強化されてしまいます。
第2章:キャリアの停滞が引き起こす「心のモヤモヤ(嫉妬)」
自己肯定感の危機に加え、彼女たちの態度の裏側には、過去の自分と現在の他者を比較してしまう、痛々しい「嫉妬の構造」が潜んでいます。キャリアの停滞期は、この嫉妬を増幅させます。
ワーママへの「ねじれた感情」の正体:諦めと未練
仕事と育児を両立させているワーママは、彼女たちにとって**「過去の自分が諦めた可能性」**を体現しているように見えます。
- 過去の選択の否定: 彼女たちが若い頃、結婚や出産などでキャリアの選択を迫られ、昇進や専門性を断念した経験があるかもしれません。その際、「両立は無理だ」と判断した過去がある場合、後輩が「時短」や「リモート」といった柔軟な働き方で成果を出しているという事実は、自身の過去の選択を否定されているように感じさせます。
- 「不公平感」の爆発: 自分が多くの時間や犠牲を払って今の地位を築いたと思っているのに、後輩が「楽な働き方」で優遇されているように見えると、「努力が足りないのに報われている」という強烈な不公平感が生まれてしまいます。この内的な葛藤が、攻撃的な態度となって外部へと噴出するのです。
「私の方が頑張ってきたのに」論理と危機感
努力しても昇進や昇給が頭打ちになり、「頑張りが報われない」と感じ始めると、その不満はどこかに向けられます。これは、彼女たちの**「努力のインフレ」**が原因です。
- 努力の価値の目減り: 長年かけて積み上げてきた「努力」や「知識」の価値が、新しいスキルを持った若手の短い期間の成果で相対的に目減りしているように見える。これは、自分の努力が「ムダ」だったかのように感じさせ、大きな怒りや焦りにつながります。
- 新メンバーへの警戒: ITリテラシーが高い若手や、効率的な働き方をする同僚は、「自分の居場所を奪う脅威」と無意識に認識されます。彼女たちの効率的な働き方は、**「楽をしている」と見なされ、かつての「長時間労働こそ正義」という価値観を持つ彼女たちにとっては、「努力の放棄」**と映ってしまうのです。
嫉妬から「指導」へのすり替え
嫉妬や不満といったドロドロした感情は、そのまま表現されません。人間は、自分の感情を正当化するために、必ず**「相手のためを思って」**という言葉のオブラートに包んで表現します。
- 「親切の皮をかぶった攻撃」: 「あなたのためを思って言っているのよ」「これは伝統だから、まずは教わらないと」といった言葉は、嫉妬や支配欲を**「指導」という大義名分**にすり替えています。
- 目的は支配: その目的は、相手を正しく導くことではなく、「私のやり方を認めなさい」「私がいなければあなたはダメでしょう」という支配欲を満たし、自分の内面の不安定さを一時的に解消することにあります。彼女たちの言葉の裏にある「本音」を見抜くことが、冷静な対処の第一歩です。

第3章:組織・マネジメント層の「見て見ぬふり」が彼女たちを増長させる
個人の心理がどうであれ、「お局」という現象が長期間続くのは、組織がそれを許容し、構造的に放置してきたからです。ここからは、管理職や組織の視点から見た「沈黙の責任」について掘り下げます。
マネージャーが「面倒くさい」と逃げた結果
多くの管理職にとって、ベテラン社員の行動変容を促すことは、最も面倒で時間がかかる問題です。そのため、多くの管理職は短期的な業務の平穏を優先し、問題の根本解決を避け、結果的に彼女たちを増長させてしまいます。
- 「放置コスト」の増加: OJTや指導に時間を割くよりも、「言っても無駄だから」と無視する方が、その時点では楽だと判断してしまう。しかし、その「放置コスト」は、後輩の離職や士気の低下という目に見えない形で組織全体に蓄積されます。
- 忖度と孤立: 彼女が組織内で築き上げた人脈や、「昔からの事情」を知る立場にあることで、管理職が忖度し、問題提起そのものをためらうケースも少なくありません。マネージャーが逃げることで、彼女たちの相手をする**「厄介な役割」**は、すべて現場の後輩や同僚に押し付けられることになります。
会社がベテランの役割を「再定義」できない問題
「お局」が誕生するのは、会社が彼女たちを**「過去の功労者」**としてしか扱えていないからです。人事評価制度が、現在の組織への貢献ではなく、過去の勤続年数や忠誠心を重んじすぎていると、問題は深刻化します。
- 評価基準の古さ: 勤続年数や「会社への忠誠心」だけで評価し続け、「今、何ができるか」という視点が欠けていると、能力に見合わない高いポジションに居座り、周りの不満を募らせます。
- 新しい役割がない: 彼女たちの豊富な経験は、「プレイヤー」としてではなく、**「メンター」や「知識の伝承者」といった、新しい専門的役割を与えることで必ず活かせます。しかし、多くの企業はその「役割の再定義」**に失敗し、彼女たちを「現場の手数」として使い続けようとします。その結果、彼女たちは「新しいこと」を学ぶ意欲を失い、既存の権威にしがみつくしかなくなるのです。
誰もが「お局」になり得る:自分の働き方を設計する教訓
この構造を理解することは、自分自身のキャリアを考える上での大きな教訓になります。組織に依存している限り、誰もが「お局」のような不安に陥る可能性があるからです。
- 社外に価値を持つこと: 組織に依存しすぎず、常に社外でも通用するスキルを磨き、自分の市場価値を意識し続けること。これが、停滞による承認欲求の肥大化を防ぐ、精神的なセーフティネットになります。
- 管理者側の責任: 「この人は手がつけられない」と諦めた瞬間に、その社員のポテンシャルと組織の健全性を同時に失います。ベテラン社員に対しては、「過去の功績を尊重しつつ、新しい貢献の形を共に探す」という、時間と労力をかけた対話が不可欠です。
おわりに:自分のキャリアを自分で守るために
「お局」の理不尽な態度は、彼女個人の資質に起因する以上に、**「変化についていけなかった個人の心理」と「ベテラン社員を適切に再配置できなかった組織の構造的失敗」**の複合的な産物です。
彼女たちの行動の「裏側」にある不安や組織の事情を知ることで、あなたは感情的に巻き込まれることを防ぎ、冷静に状況を分析するためのツールとなります。彼女たちが示すサインは、組織のどの部分に歪みがあるのかを教えてくれる、貴重なアラートなのです。
あなたの仕事のモチベーションや心の健康は、誰かの不満のガス抜きに使われるためにあるわけではありません。彼女の態度が理不尽だと感じたら、それはあなたの問題ではなく、**「彼女自身の不安」または「会社の仕組みの古さ」**だと割り切りましょう。
自分の価値は、誰かの承認や、会社の古びたルールの中にはありません。 自分の目標とプライドをしっかり持ち、もし理不尽な壁にぶつかったら、それは「自分の力が足りない」のではなく、「会社の仕組みが古い」のだと判断しましょう。自分の人生の主導権は、常にあなた自身が握っていることを忘れないでください。