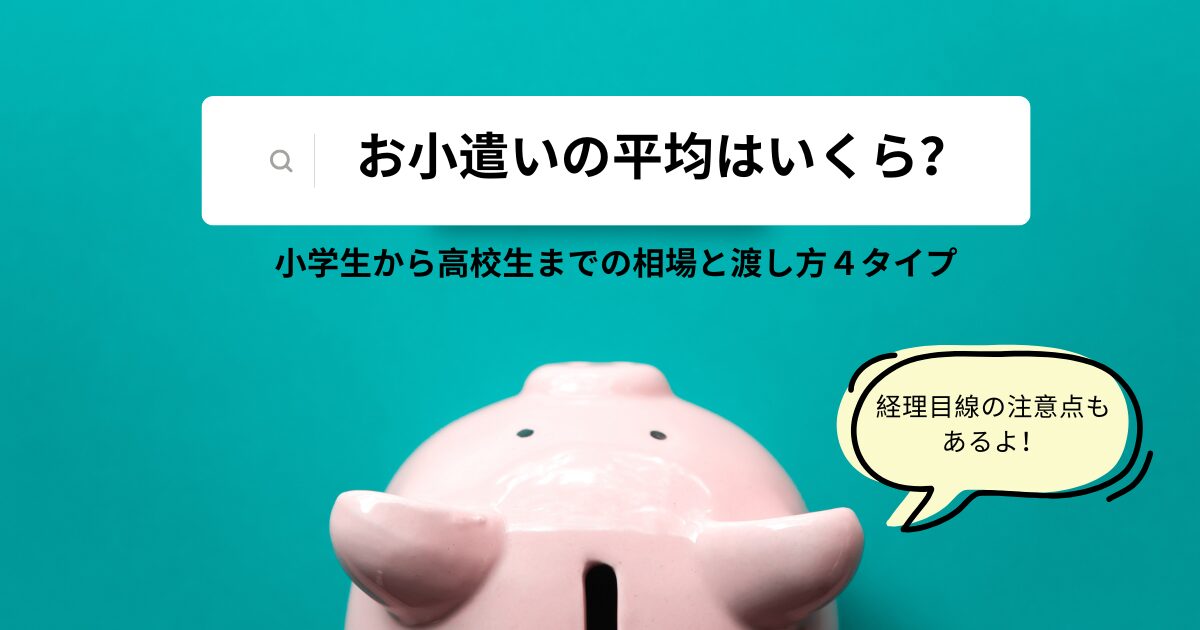目次
「子どものお小遣い、どうしてる?」
これは、親同士が集まるとよく話題になるテーマのひとつでした。
- 毎月きっちり渡す派
- 必要なときにだけ渡す派
- 手伝ったら報酬を与える派
家庭によって方法も金額もバラバラ。子どもの金銭感覚や教育方針が大きく反映される部分です。
さらに、経理や税務の知識を持つ立場から見ると「贈与税」や「名義預金」といった、将来に関わる注意点も無視できません。
今回は、調査データ・表形式の比較・親目線の体験談・経理目線のアドバイスを交えて、子どものお小遣い事情をまとめてみました。
子どものお小遣いの平均額
学研教育総合研究所「小学生白書Web版(2024年調査)」などのデータを参考にすると、平均額は以下のとおりです。
| 学年 | 月のお小遣い平均額 | 備考 |
|---|---|---|
| 小学1~2年生 | 約500円 | 駄菓子や小さなおもちゃ |
| 小学3~4年生 | 約1,000円 | 文房具・友達との遊び |
| 小学5~6年生 | 約1,500~2,000円 | ゲーム・趣味も含む |
| 中学生 | 約2,500~3,000円 | 部活・スマホ代など |
| 高校生 | 約5,000~7,000円 | 交際費・ランチ代など |
💡以外にも高いというのが、私の印象です。あくまで平均値であり、「家庭の方針」「地域差」「子どもの交友関係」によって幅があります。特に中高生になると、友人関係やスマホ代、塾や部活の費用などで必要額が一気に膨らむ傾向があります。
お小遣いの渡し方4タイプ
お小遣いの渡し方には大きく分けて4タイプあります。
| 渡し方 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 定額制 | 毎月決まった額を渡す | 計画性が育ちやすい/親子で管理がしやすい | 「努力」と結びつかず、当たり前になりがち |
| 報酬制 | 家事や勉強などを手伝ったら渡す | 働く価値を学べる/モチベーションにつながる | 仕事をしないとゼロになる/親が管理に疲れる |
| ハイブリッド制 | 基本は定額+手伝いで追加 | バランスが良く柔軟/教育効果が高い | 管理の仕組みづくりが必要 |
| その都度制 | 必要なときに必要な分だけ渡す | 管理がラク/浪費を防ぎやすい | 金銭感覚が育ちにくい/計画性がつきにくい |
わが家の体験談
小学校低学年のころ
最初は「その都度制」でした。お菓子や文房具を買うときに100円を渡す程度。親にとっては気楽でしたが、子どもが「今日はもらえるかな?」と期待するようになり、ちょっとした駆け引きが面倒になることもありました。
正直、金額も大きくありませんでしたので、お小遣いを渡す必要性をあまり感じていませんでした。
高学年になってから
友達と遊びに行くことが増え、「いくら持って行っていい?」と毎回聞かれるのが負担に…。そこで「定額制」に移行しました。
さらに中学に入ると、欲しい物も多様化。そこで我が家では「ハイブリッド制」を導入しました。
- 毎月2,000円を定額で渡す
- 家事(洗濯物を畳む、掃除をするなど)をすると、内容によって追加で100円~200円
- お年玉は、基本自分で管理(金額は把握していました)
この方法にしてから、子どもは「今月はゲームのために貯めておこう」と計画的に考えるようになり、家事も積極的にやるようになりました。
中学生から高校生
部活動や友達との外出も増えていましたので、金額は3,000円から5,000円。必要なものや、特別な外出の際には、都度渡していました。
お年玉も自分で管理していましたので、欲しいものがある時は自分で考えながら購入していたようです。管理や購入は任せていましたが、高額と思われるものを購入する場合は、事前に相談するよう話していました。
大学生から現在の金銭事情と考え方
大学に入れば、学費やアパート代などは親が支払いを行っていましたので、基本お小遣いはアルバイトをしながら自分で何とかしていました。
小さい頃から金銭感覚を身に着けていたことで、社会人になってからは、現在のお金・将来のお金と考えながら生活しているようです。NISAや投資信託など、自分で運用も行っています。
💡それぞれの子どもの性格で、お金に関する認識の違いもあります。現在は一切口出しすることはありませんが、会話の中でお金に関する話題が出来るような雰囲気を作ることも必要だと考えます。
***お金にまつわる記事です***
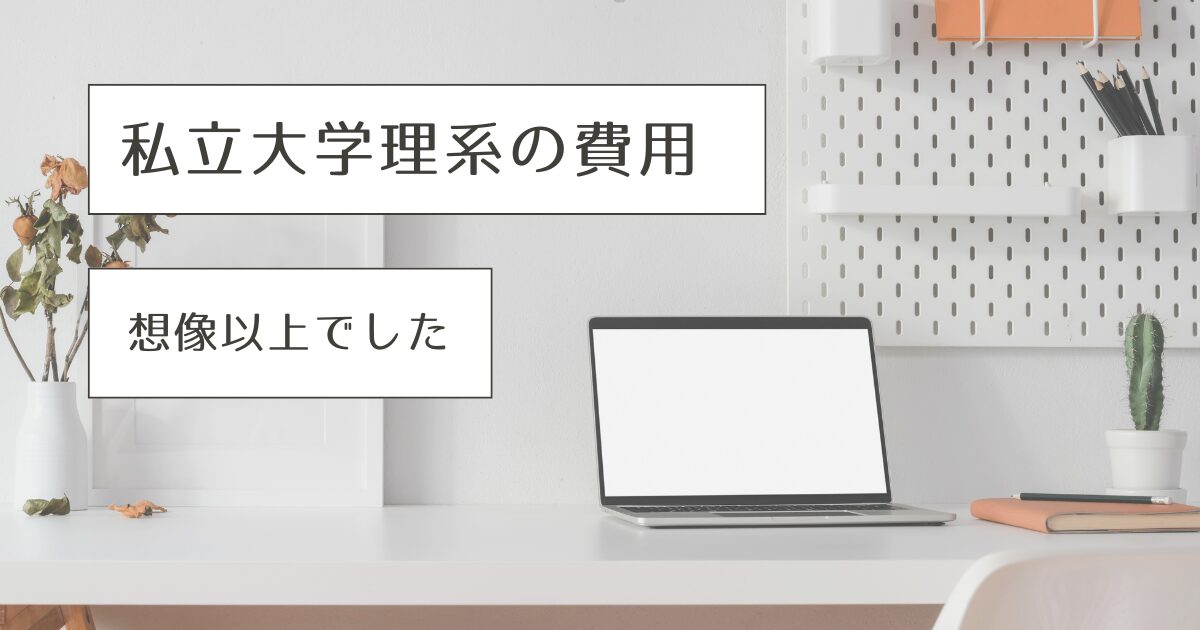
経理目線で見たお小遣いの注意点
一見シンプルなお小遣いですが、金額が大きくなると税務的な問題も出てきます。
- 年間110万円以上の贈与は課税対象
祖父母からの教育資金援助などが典型例。お小遣いレベルでは心配ありませんが、塾代や留学費用をまとめて援助する場合は要注意。 - 高価な品は現物支給扱い
例えば「最新スマホ」「高額ブランド品」など。お金を渡さなくても、財産を贈与したことになります。 - 名義預金に注意
「子ども名義の口座に毎月積み立て」していても、実際の管理者が親なら「親の資産」とみなされる可能性があります。将来の相続税に影響するため要注意です。
💡 まとめると
お小遣いレベルなら問題はありませんが、「学資資金」「高額援助」「長期間の預金」などになると課税や相続の対象になる可能性がある、ということを覚えておきましょう。
子どものお小遣いルール チェックリスト
最後に、家庭でお小遣いルールを決めるときのチェックリストを用意しました。
- 定額制・報酬制・ハイブリッド制・その都度制のどれを採用するか決めている
- 金額は「平均額」を参考にしつつ、家庭の事情に合わせている
- 使い道のルールを設定している(お菓子・ゲーム・交際費など)
- 家計や子どもの理解度に応じて、段階的に金額を調整している
- お金の使い方を記録・管理する方法(ノートやアプリ)を一緒に決めている
- 貯金の習慣を持たせる工夫をしている
- 経理・税務の知識(贈与・名義預金など)を親が理解している
まとめ
お小遣いは、単なる「お金のやりとり」ではなく、家庭の教育方針を映す鏡です。
- 平均額や相場を知る
- 渡し方のスタイルを選ぶ
- 家庭に合ったルールを作る
- 経理の知識を少し押さえておく
この4つを意識することで、子どもに健全なお金の感覚を育てることができます。
お小遣いをきっかけに、子どもと「お金の話」をオープンにできる家庭を目指していきたいですね。