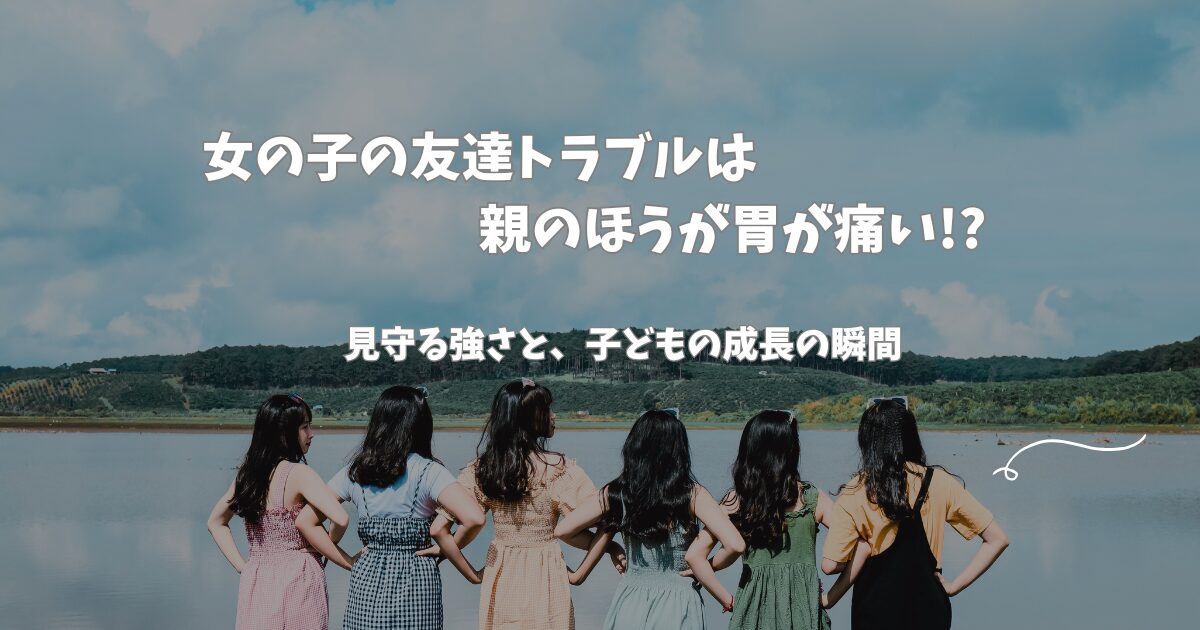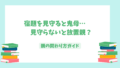目次
「今日、〇〇ちゃんと口きかなかったの」
「でももう仲直りしたよ」
娘がケロッとした顔で話しても、母親の胸はザワザワ。
頭では「子ども同士のこと」と分かっていても、心は落ち着きません。
実際、**女の子の友達関係トラブルで一番消耗しているのは“母親のほう”**ではないでしょうか。
私も娘の友達関係では小さい頃から悩みが多く、眠れない日もありました。今考えれば、悩むようなことではなかったかもしれないのですが、その時は悲しみや苦しみでいっぱいでした。
この記事ではそんな経験をもとに、今をどう乗り切るか、そして未来にどうつなげるかをお話しさせていただきます。
■ 女の子の世界は“空気”で変わる
小学生〜中学生の女の子の友達関係は、驚くほど複雑です。
昨日まで笑い合っていたのに、次の日には無視されている。
「3人グループ」のバランスが崩れただけで、あっという間に“誰かが浮く”構造になる。
男子のようにケンカしてスッキリ、ということが少なく、
表面は笑顔でも、内側で静かな圧力がかかるのが女の子の世界。
親から見ると「なんでそんなことで…」と思うけれど、
本人たちにとっては“世界の終わり”くらい深刻なのです。
■ 見守るしかない親の苦しさ
母親としては、つい手を出したくなります。
「どうしたの?」「なんでそんなこと言われたの?」
「そんな子と付き合わなくていいよ」と口にしてしまう。
けれど、実際にそれでうまくいくことはほとんどありません。
むしろ、親が関わることで娘が「大げさに言った」と責められたり、
関係がさらに悪化することも。
結局、親は見守るしかない。
でも、それが一番つらいんです。
本人よりも母親のほうが胃が痛くなる理由は、“守れない無力感”にあるのだと思います。
■ 女の子特有の“つながり”の強さと疲れやすさ
心理学的にも、女の子は幼少期から「共感でつながる」傾向が強いといわれています。
「同じ気持ち」「同じ立場」でいることで安心し、
そこから外れると「裏切られた」と感じてしまう。
これは大人の女性社会にも少し通じるところがありますね。
ランチ仲間、LINEグループ、PTA…。
“共感”がつなぐ関係はあたたかい反面、少しの違いで不安や疎外を感じやすい。
だからこそ、娘がその“人との距離感”を早くから学ぶことは、
将来の人間関係を生きやすくする大事なステップでもあります。
***関連記事***

■ 親が「してはいけない」3つのこと
娘がつらい思いをしているとき、親の対応ひとつで関係が長引くこともあります。
以下は、実際の教育・心理の現場でもよく言われる「NG対応」です。
相手の親に直接連絡する
気持ちは分かります。けれど、子ども同士のトラブルに大人が入ると、
子どもたちは「自分たちの問題じゃなくなった」と感じ、関係修復のチャンスを失います。
「そんな子とは付き合わなくていい」と言う
この言葉は一見正論ですが、子どもに「私が悪いのかな」という罪悪感を残すことも。
人間関係の引き算は、本人が納得してできるようになることが大切です。
親の気持ちを優先してしまう
「なんでそんなことされて黙ってるの?」
「あなたが我慢しすぎなんじゃない?」
親の“正義”を押しつけると、娘はさらに話しづらくなってしまいます。
■ 親が「できること」は“共感”より“安心”
では、親はどう関わればいいのでしょうか。
キーワードは「共感」よりも「安心」です。
話したくなったら話せる空気をつくる
無理に聞き出そうとせず、
「今日もお疲れさま」「話したいときは聞くからね」
と“いつでも話していいよ”というスタンスを保つ。
「解決」ではなく「回復」をサポート
友達関係の修復は、親が動いても進まないことが多いです。
それよりも、娘が“自分を取り戻す”時間を支えるほうが有効。
好きなことに打ち込む、趣味を一緒に楽しむなど、心の回復にエネルギーを使いましょう。
「どんな結果でもあなたの味方」という軸を伝える
「またトラブルになった」と落ち込む娘に、
「大丈夫。どうなっても、ママは味方だよ」と伝えるだけで、
子どもは自分で立ち直る力を取り戻します。
■それでも、うまくいかないときもある【体験談】
とはいえ、どんなに見守っても、
友達関係の波がすぐにおさまるとは限りません。
特に女の子の世界は、“その日その瞬間の空気”で変わることも多いもの。
親としては、なんとか守ってあげたくなるけれど、実はこの“トラブルを経験すること”こそが、
子どもが人との距離感や自分の立ち位置を学ぶ大切な機会でもあります。
以前書いた
👉 「苦手が多い子が見せてくれる思いがけない成長」
でも触れましたが、うまくいかない時期ほど、子どもは内面で大きく成長しているものです。
学生時代、勉強も実技も周囲についていけず、自分なりの方法で目標に向かっていったという記事なのですが、実はこれには裏話があります。
実技が苦手な娘は、できることから始めようと、毎日勉強にもくもくと取り組み成績が上がることで自信となり、苦手を克服していったのですが、、、。
毎日のように学校が終わると、図書館で一人勉強をするようになったことで、仲の良かったグループからハブられることになります。娘の成績が伸びていくことも気に入らなかったのでしょう。
でも、小さな頃から様々な友達トラブルを自分で乗り越えてきたことで、その時も動じることなく、ひたすら自分の目標に向かって集中していったことは、卒業後に聞くことになります。
「あの泣き虫で人の目ばかり気にしていた子がこんなに強くなれるんだ。」と本当に驚きました。
友達とうまくいかない経験も、
“人に合わせすぎない強さ”や“自分の考えを持つ力”を育ててくれることがあります。
親ができるのは、その痛みを“成長の途中”として見守ること。
守るよりも、強くなれるよう支える視点が大切だと実感しました。
■成長の波を“信じて待つ”というサポート
子どもの友達トラブルは、親にとって試練でもあります。
けれど、少し長い目で見てみると、
「その時期を通ったからこそ強くなれた」と思える瞬間が必ず来ます。
泣きながら登校していた子が、数ヶ月後には別の友達と笑っている。
あのときの涙が、確かに“生きる力”に変わっていくのです。
■親の心のケアも忘れずに
子どものトラブルに寄り添うと、親も心身が疲れます。
「なんでうちの子ばかり」「どうしてこんなに悩むんだろう」
そんな気持ちになったときは、少し距離をとる勇気も必要です。
ママ友や家族に話す、好きなことをする、少し外の空気を吸うだけでも気持ちは軽くなります。
親が穏やかでいることこそ、子どもにとって最大の安心材料です。
■まとめ:子どもは“守る”より“信じて育つ”
女の子の友達関係トラブルは、母親の心を最も揺さぶるテーマかもしれません。
でも、そこで学ぶことが、人との距離の取り方や思いやり、強さにつながっていく。
子どもが悩んでいる姿を見るのは苦しいけれど、親が「信じて見守る」ことも、立派なサポートの形。
今日も少しだけ胃が痛くても、その痛みの先に、確かな成長があります。