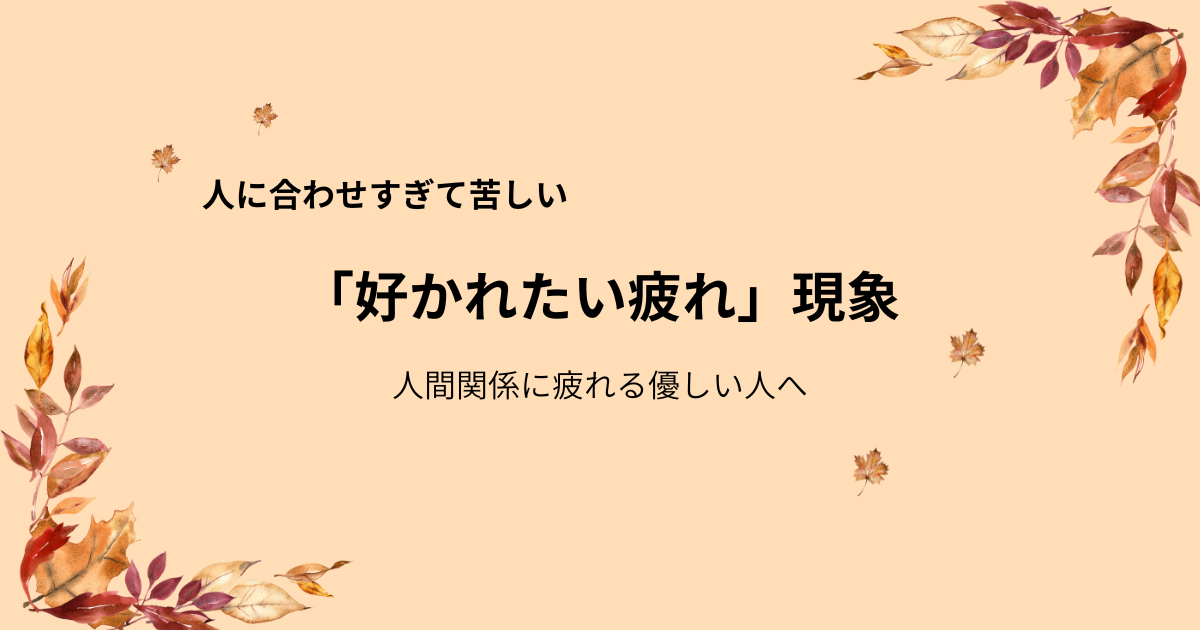目次
「人から嫌われたくない」
多くの人が、そう感じたことがあるのではないでしょうか。
職場での人間関係、ママ友との距離感、SNSでの発言ひとつにさえ、
「これ言ったらどう思われるかな」と頭をよぎる。
実は、これはとても自然なことです。
人間は社会的な生き物で、集団の中で生きていくために「好かれたい」という本能を持っています。
けれども、その“好かれたい”が強くなりすぎると、人との距離が逆に苦しくなる。
それがいま、静かに広がっている「好かれたい疲れ」現象です。
私も同じでした。周囲の目ばかり気にして、言いたいことも言えないことが多かった。でも、年齢と共に自分らしくないと気づいて、少しずつ変わっていきました。
■“好かれたい”がやめられない人の特徴
「好かれたい」という感情は、一見ポジティブです。
周囲に気を配り、空気を読み、協調性を持って動ける人は、組織でも重宝されます。
しかし、人事や現場で見てきた中で感じるのは——
“好かれたい”人ほど、実は疲弊していくという現実。
たとえばこんな傾向があります。
- 断ることができず、つねに誰かのサポートに回っている
- 「あの人にどう思われたか」がずっと気になる
- トラブルを避けるために、意見を飲み込む
- 評価されるより、“嫌われない”ことを優先してしまう
一見、周りとうまくやっているように見えますが、心の中は「我慢」「空回り」でいっぱいです。
■なぜ“好かれたい”がやめられないのか
背景には、いくつかの心理的要因があります。
承認欲求の強さ
誰かに「ありがとう」と言われることで自分の存在価値を感じるタイプです。
承認が一時的な“ごほうび”になり、繰り返し求めてしまいます。
過去の人間関係の傷
子どものころに「いい子ね」と言われ続けた人ほど、
“いい人”でいようとする傾向があります。
裏を返せば、「いい人でいないと嫌われる」という不安の裏返し。
自己評価の低さ
自信がない人ほど、人の評価に依存しやすくなります。
自分を信じるより、他人の反応を基準にしてしまうのです。
こうした心理は、誰にでも少なからずあります。
問題は、それが“自分の軸”を見失うほど強くなったときです。
■「好かれること」と「信頼されること」は違う
ここで一度、立ち止まって考えたいのがこの言葉。
好かれることと、信頼されることは違う
「好かれよう」とする人は、相手の期待に応えることを優先します。
でも「信頼される人」は、相手に都合のいいことばかり言いません。
必要なときには、耳の痛いことも伝える。
その違いが、時間の経過とともに人間関係の“質”を分けていきます。
信頼される人は、必ずしも全員に好かれるわけではありません。
でも「この人の言葉なら信じられる」という安心感を持たれます。
一方、好かれようとする人は、誰にでも合わせてしまうため、結果として“軽い存在”に見られがちです。
■“好かれたい疲れ”が引き起こす3つの弊害
自分を見失う
「どの自分が本当の自分かわからない」状態になります。
相手によって言葉や態度を変えるうちに、自分の本音がどこにあるのかわからなくなってしまう。
境界線がなくなる
他人の機嫌に左右されやすくなり、自分の時間やエネルギーを奪われます。
「頼まれたら断れない」「自分の予定を後回しにする」など。
表面的な関係しか築けない
誰にでも合わせる人は、トラブルを避けやすい反面、“深い関係”にはなりにくい。
人は、弱さや本音を共有して初めて信頼関係を築けるのです。
***関連記事***

■“好かれたい”から“信頼されたい”へシフトする3ステップ
ステップ① 「嫌われてもいい」と思ってみる
完全に嫌われたいわけではありません。
ただ、「誰かに合わない自分」を受け入れる練習をするのです。
人は十人十色。
どんなに感じの良い人でも、苦手とする人は必ずいます。
「全員から好かれることは不可能」と自分に言い聞かせるだけで、心がふっと軽くなります。
ステップ② 本音を小出しにする
いきなり主張を強めるのではなく、
「私はこう思うんだけど」と“自分の意見を添える”習慣をつけます。
たとえば、会議での一言、LINEでの返信、家族とのやり取りなど。
最初は勇気がいりますが、本音を小さく伝えることで、「この人は信用できる」と思われることが増えていきます。
ステップ③ “人の反応”より“自分の納得”を基準にする
「どう思われたか」よりも、「自分は納得できたか」で判断してみましょう。
誰かに合わせて疲れるより、自分の気持ちを大切にするほうが、結果的に誠実な関係を築けます。
たとえば職場でも、
“八方美人”よりも、“自分の言葉で話す人”のほうが信頼を得ています。
■人事の現場で見た「信頼される人」の共通点
長年、経理・人事の現場で働く中で、
「この人は信頼されているな」と感じる人には共通点があります。
- 誰に対しても態度が変わらない
立場や役職によって態度を変えない人は、周囲に安心感を与えます。 - 感情よりも筋を通す
“いい人”ではなく、“正しい人”であろうとする。
時には意見がぶつかっても、筋の通った人は結果的に信頼されます。 - 自分の弱さを隠さない
完璧を装うより、「自分もミスする」と素直に認める人のほうが、
人間味があり、周囲も心を開きやすい。
「好かれよう」として気を使うより、「信頼されよう」として誠実でいるほうが、
長い目で見ればずっと関係は穏やかに続くのです。
■“いい人”をやめた瞬間から、関係が楽になる
自分自身もかつて、「嫌われたくない」タイプでした。
頼まれると断れず、周囲の空気を読みすぎて自分を消していた時期があります。
でも、ある日ふと気づきました。
「私が本音を言えない関係は、そもそも信頼関係じゃない」と。
そこから、少しずつ「NO」を言う練習を始めました。
最初はギクシャクしたけれど、不思議と本音を言ったあとのほうが、周囲との関係が“正直”になっていったのです。
“いい人”をやめたら、周りの人も「本当の私」を見てくれるようになりました。
そして、「無理しなくていいんだ」と思えるようになったとき、人間関係のストレスがすっと減ったのを覚えています。
■「誰からも好かれなくていい」けど、「自分には好かれていたい」
究極的には、人間関係の原点はここにあります。
他人の評価より、自分の自己評価
誰からも好かれる必要はありません。
でも、自分が自分を嫌いになってしまうような無理や我慢を続ける関係は、長続きしません。
「自分を裏切らない」こと。
それが、信頼関係のいちばんの基礎です。
■おわりに:好かれようとしなくても、人はつながれる
「好かれたい」と思うことは、決して悪いことではありません。
ただ、その思いが自分を苦しめるほど強くなっているなら、少し立ち止まってみましょう。
誰からも好かれなくていい。
でも、自分が納得できる人間関係でいたい。
そう思えるようになったとき、あなたの表情や言葉に、自然と“信頼の色”がにじみ出てきます。
そして、不思議なことに——
そんなあなたを見て、「この人と一緒にいたい」と思う人が、少しずつ集まってくるのです。
🪞まとめ
「好かれたい疲れ」は、優しい人ほど抱えやすいもの。
でも、人の目ばかり気にして生きていると、いちばん大事な“自分の声”が聞こえなくなってしまいます。
無理をやめたとき、本当に気の合う人とのつながりが生まれる――
それが、人間関係を楽にする第一歩なのかもしれません。